 |
|
 |
|

私が今までに執筆・編集などを手がけた本を紹介します。
最新のもの
|
|
|
タイトル |
発行日出版社
|
内容 |
|
|
『男が「よよよよよよ」と泣いていた』(日本語は感情オノマトペが面白い)
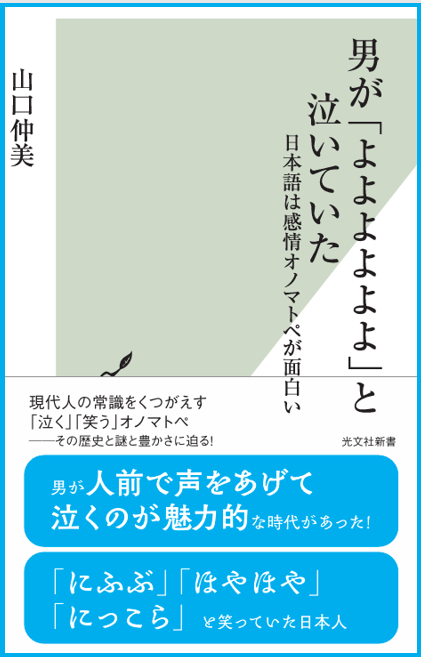
単著
|
2025年8月
光文社新書 |
男が人前で大声をあげて泣くなんて、現代ではちょっとカッコ悪い。でも、オノマトペを調査追究して行くと、男が大声をあげて子供のように泣くのが魅力的だった時代があった! 笑い声も、男が「ほほ」と笑うのが普通だった時代があった。いつ? なぜ? 現代人の意表を突く新事実が詰まっています
| |
|
『千年たっても変わらない人間の本質』(日本古典に学ぶ知恵と勇気)
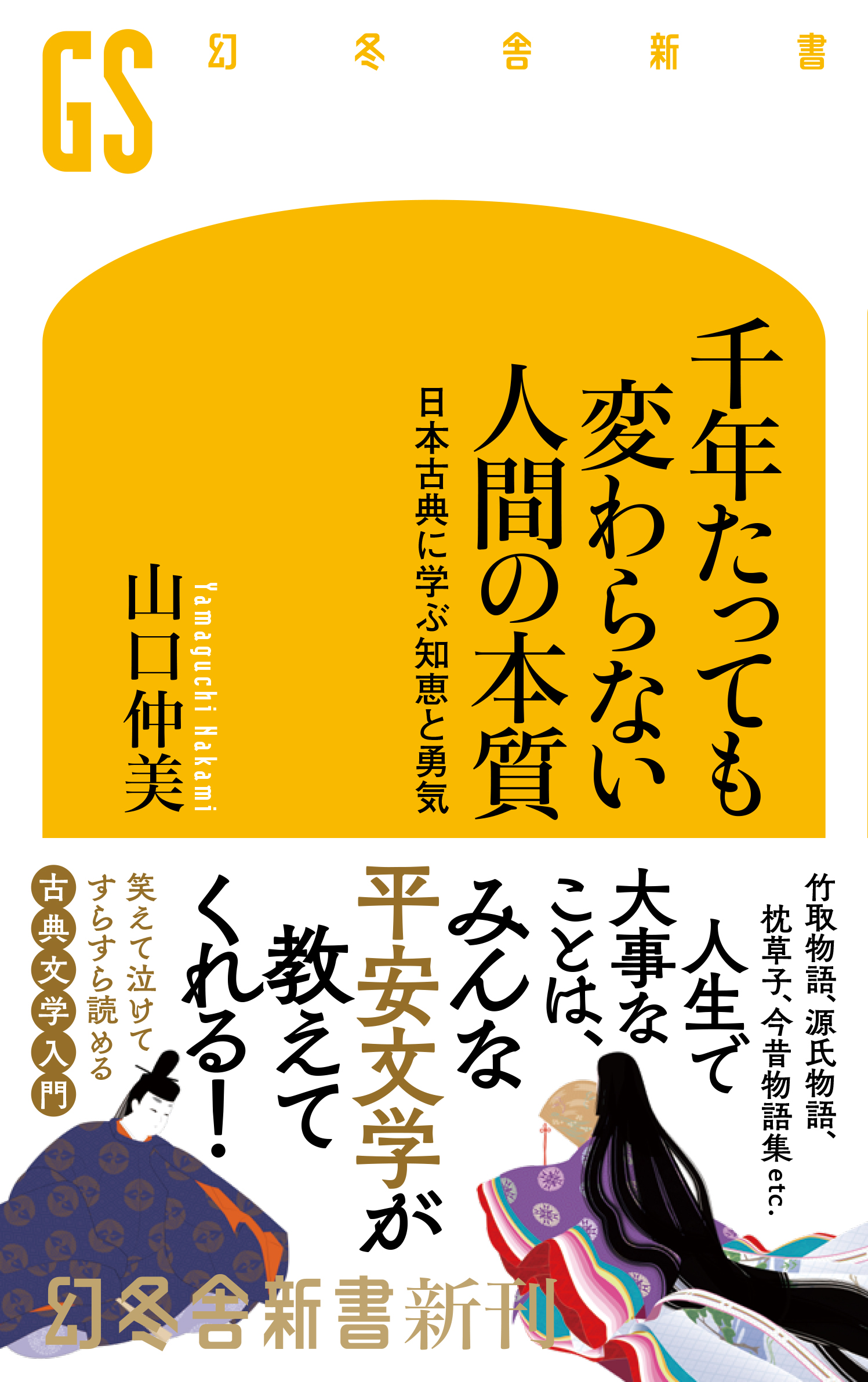
単著
|
2024年5月
幻冬舎新書 |
現代の私たちが生きるための知恵と勇気を、平安時代の古典から学び取ろうとする本です。恋愛に戸惑っていたり、結婚生活に悩んでいたり、変人扱いされて困っていたり、部下を統率できずに悩んでいたり、そんな現代の人々に、『源氏物語』『枕草子』『大鏡』などの良く知られた古典が知恵と勇気を与えてくれます。
| |
|
『日本語が消滅する』
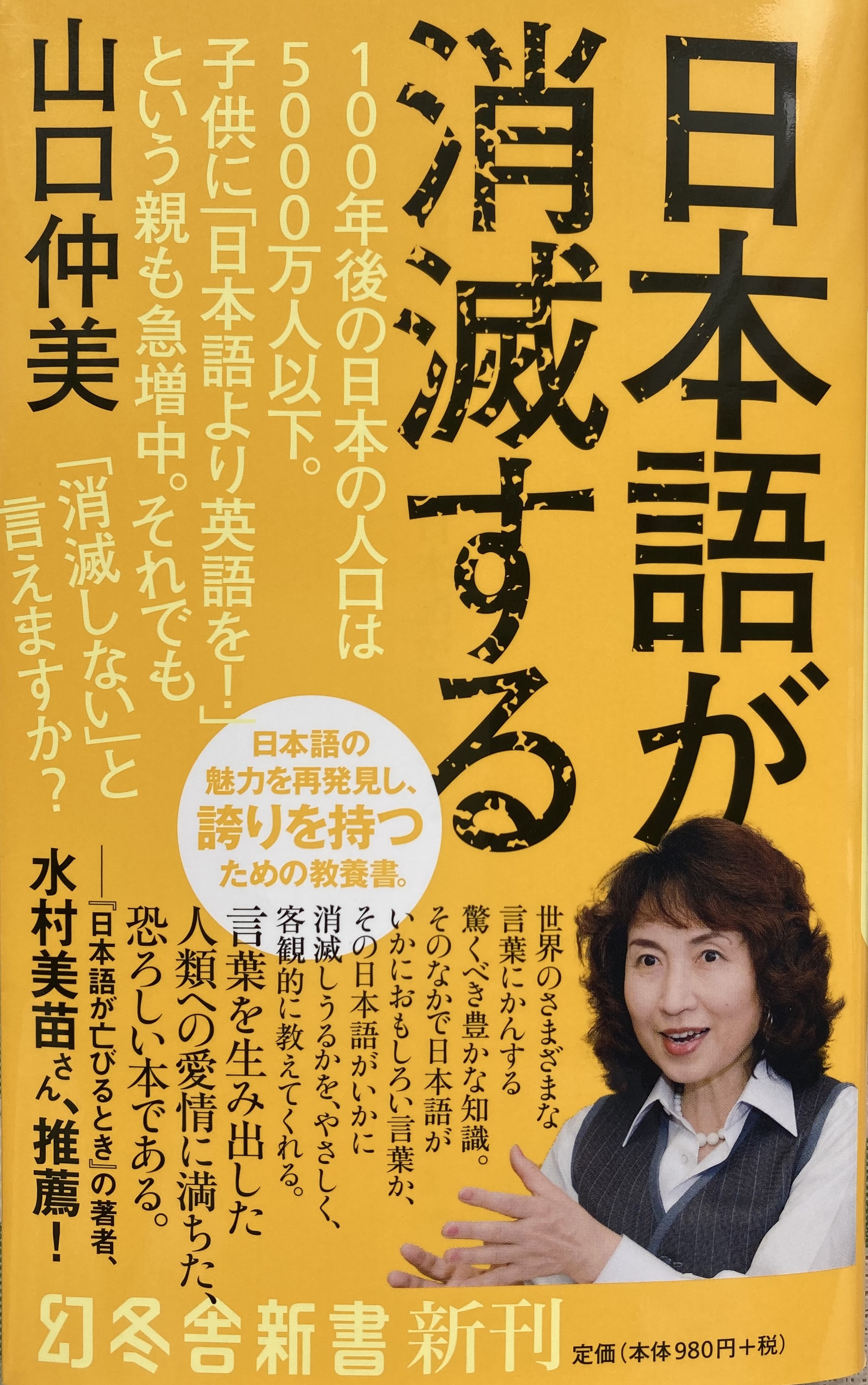
単著
|
2023年6月
幻冬舎新書 |
ショックなタイトルで申し訳ありません。でも、読んでいただくと、世界的な視野から、日本語の面白さ・底力を確信できます。残さなければならない貴重な言語です。そうした日本語の消滅を防ぐ手立ても納得していただける気がします。
| |
|
『犬は「びよ」鳴いていた』
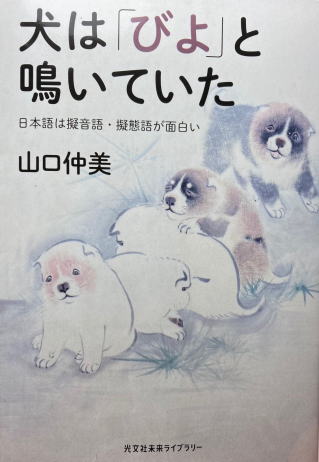
単著
|
2023年5月
光文社未来
ライブラリー |
2008年8月に出した『犬は「びよ」鳴いていた』の文庫化です。図版も全て新しく撮りなおし、文章も補筆、修正してあります。なんと女子高校生がこの本の読書感想文を書いて「毎日新聞社賞」を獲得したのです。嬉しかったですね、高校生が読んでくれていたわけですから。 |
|
|
『すらすら読める枕草子』
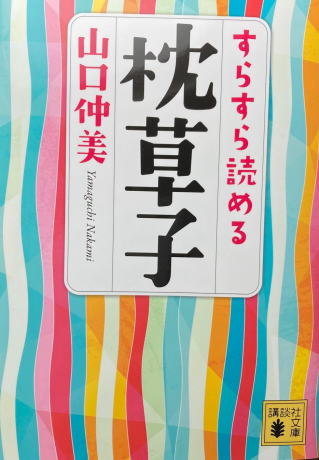
単著
|
2023年3月
講談社文庫 |
2008年6月に出した『すらすら読める枕草子』の文庫化です。表紙の色合いが派手で気にっています。『枕草子』のなかから、男と女のエチケット、人としてのマナーに関する章段をとりあげて口語訳と解説を加えたものです。楽しめること請け合いです。 |
|
|
『現代語の諸相2』
(言葉の探検・
コミュニケーション実話)
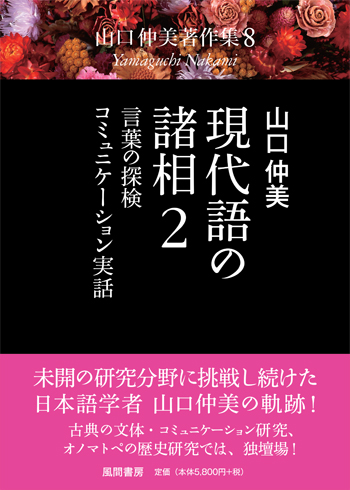
単著
山口仲美著作集8 |
2020年9月
風間書房 |
著作集8『現代語の諸相2』は、ユニークな言葉、中国人や医者とのコミュニケーションをとりあげ、エッセイタッチで書いた単行本を収録している。Ⅰ部は、「言葉の探検」。ドキッとするような言葉や表現をとりあげ、その特性を解明。Ⅱ部は、「言葉の先生、北京を行く」。中国人の大学教師・リーさんを中心に、彼らのコミュニケーション術やその能力の高さにたじたじとなる話を収録。Ⅲ部は、「大学教授がガンになってわかったこと」。命に係わる選択を、どのようなコミュニケーションで解決したのか。納得のいく治療を受けるための患者の心得を伝授。Ⅳ部は、「身辺エッセイ&経歴」。身の回りで起きた出来事、私の出会ったステキな先生、日々の思いなどを綴る。最後に、著者のこれまでの歩みを網羅した経歴を収めた。
『山口仲美著作集』→今すぐ購入したい方はこちらへ
|
|
|
『現代語の諸相1』
(若者言葉・ネーミング・
テレビの言葉ほか)
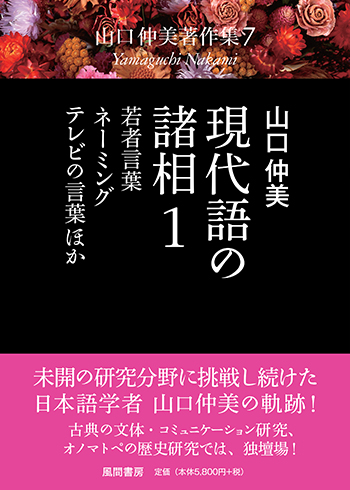
単著
山口仲美著作集7
|
2020年5月
風間書房 |
著作集7『現代語の諸相1』は、現代語をテーマにした著書・論文・エッセイを収録。四部立て。Ⅰ部は、「若者言葉に耳をすませば」。本音全開の座談会を中心に、若者言葉の特色を明らかにしたもの。Ⅱ部は、「ネーミングと広告」。命名行為の秘密を解くカギの詰まった「あだ名」。傑作な「あだ名」の条件とは? Ⅲ部は、「テレビの言葉」。刻々と変わりゆく言葉の先端を視聴者の立場とテレビを作る立場からとらえたもの。出題された問題を解いてみると面白い。Ⅳ部は、「現代語の問題&エッセイ」。日本語教育や敬語表現、言葉の力などに関する論やエッセイを収録。
『山口仲美著作集』→今すぐ購入したい方はこちらへ
|
|
|
『オノマトペの歴史2』
(ちんちん千鳥のなく声は
犬は「びよ」と鳴いていた)
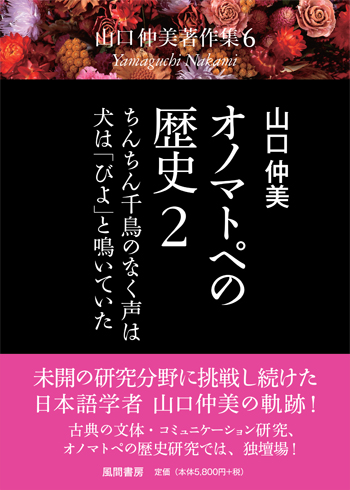
単著
山口仲美著作集6
|
2019年12月
風間書房 |
著作集6『オノマトペの歴史2』は、鳥の鳴き声や獣の声を写すオノマトペ(=擬音語)の推移を解明した著書を収録。Ⅲ部から成る。Ⅰ部は、「ちんちん千鳥のなく声は」。Ⅱ部は、「犬は『びよ』と鳴いていた」。Ⅲ部は、「オノマトペ研究余滴&エッセイ」。カラスの声やウグイスの声、はたまた、犬や猫の声を写す言葉は? みんな知っていると思っているのだが、歴史を遡っていくと、現代人の予想もしなかった愉快な世界が開けている。Ⅲ部には、妖しげな言葉「ちんちんかもかも」はどこから出て来た言葉? 「ひゅうどろどろ」は、なぜお化けの出る合図に? オノマトペがあるからこそ可能になる豊かな日本語の世界がここに。
『山口仲美著作集』→今すぐ購入したい方はこちらへ
|
|
|
『オノマトペの歴史1』
(その種々相と史的推移
「おべんちゃら」などの語史)
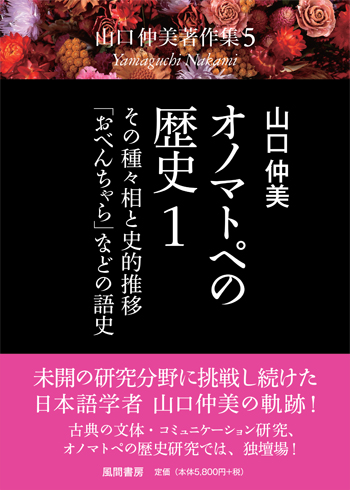
単著
山口仲美著作集5
|
2019年10月
風間書房 |
この巻は、オノマトペ(=擬音語・擬態語)のさまざまな性質や史的推移を明らかにした論文やエッセイを収録。ⅠⅡⅢの三部から成る。一部は作品別・ジャンル別にとらえた時に顕著に現われるオノマトペの特色・機能を明らかに。コミックにみられるオノマトペはどんな特色を持っているのか?Ⅱ部は、男女の泣き方を表すオノマトペ、動物の声を写す擬音語、楽器の音を表す擬音語などの指摘推移を追究。Ⅲ部は、「いちゃもん」「おべんちゃら」「どんぶり」「パチンコ」など、オノマトペにルーツを持つと思われる言葉を対象に、その語史を追究。びっくりするような言葉のルーツが明らかに。
『山口仲美著作集』→今すぐ購入したい方はこちらへ
|
|
|
『日本語の歴史・古典』
(通史・個別史・日本語の古典)
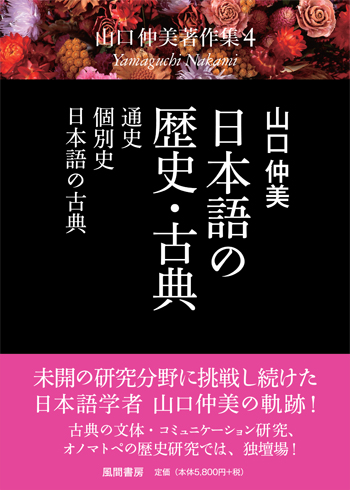
単著
山口仲美著作集4
|
2019年5月
風間書房 |
第四巻は、岩波新書『日本語の歴史』・『日本語の古典』として刊行されている単行本も収録されていて、楽しめる巻になっていると思う。全体は、ⅠⅡⅢの三部構成。Ⅰ部は、「日本語の歴史―通史―」。新書でおなじみの『日本語の歴史』を収めて部分。Ⅱ部は、「日本語の歴史―個別史―」。「売薬名の歴史」や「感覚・感情語彙の歴史」などの読みやすい論文が収録されている。Ⅲ部は、「日本語の古典」。岩波新書『日本語の古典』を収めたもの。目次をご覧になって興味を持たれたところから、ぜひ、読んでいただきたい。
『山口仲美著作集』→今すぐ購入したい方はこちらへ |
|
|
『言葉から迫る平安文学3』
(説話・今昔物語集)
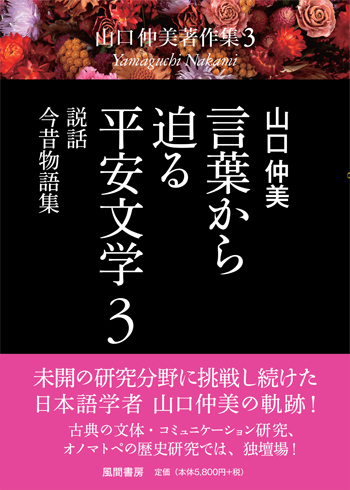
単著
山口仲美著作集3
|
2018年12月
風間書房 |
第三巻は、「言葉から迫る平安文学3 説話・今昔物語集」。ⅠⅡⅢの三部から成る。Ⅰ部は、「説話文学の言葉と文体」。従来とは違った出典文献との比較という方法で手堅く『今昔物語集』の文体に迫った論などを収録。Ⅱ部は、「『今昔物語集』の表現方法」。丸善ライブラリー『平安朝〝元気印〞列伝―今昔物語の女たち―』を収録したもの。読者を魅了してやまない表現方法の秘密を解き明かしている。Ⅲ部は、「『今昔物語集』にみる生きる力」。読者に勇気と生きる力を与えてくれる話をセレクトし、原文・現代語訳・解説を行ない、『今昔物語集』の持つエネルギーをあぶりだす。
『山口仲美著作集』→今すぐ購入したい方はこちらへ
|
|
|
『言葉から迫る平安文学2』
(仮名作品)
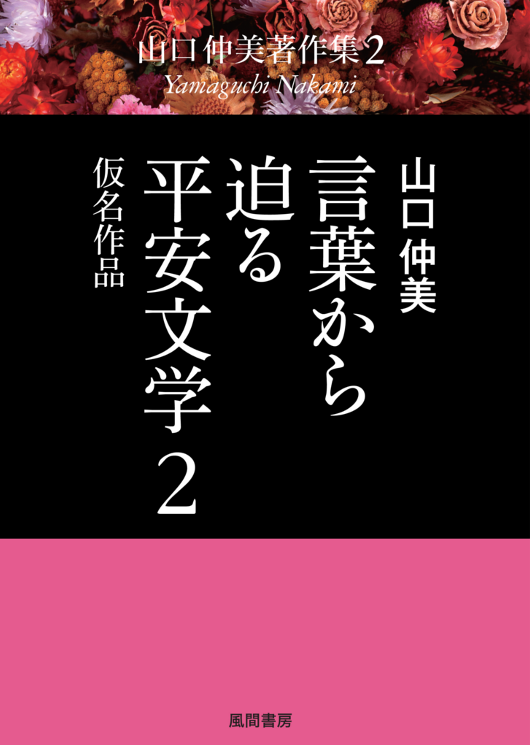
単著
山口仲美著作集2
|
2018年10月
風間書房 |
第二巻は、平安時代の仮名で書かれた『源氏物語』以外の日記・随筆・物語を対象に、言語学的側面からさまざまな問題を追究。四部から成る。
Ⅰ部は、導入部的な論。Ⅱ部は、「物語と日記の言葉と文体」。平安文学作品全体の文体にかかわる問題と、竹取物語・和泉式部日記といった個別の作品の言葉と文体にかかわる問題を取り扱う。Ⅲ部は、「『枕草子』新しい読み方」。『枕草子』をマナー集として読むという新しい読み方を提示し、『枕草子』の魅力を味わう。Ⅳ部は「研究余滴」。仮名文学作品を読んでいて、疑問に思ったこと、感動したこと、主張したくなったことなどを、エッセイ風にまとめたものを収録。
『山口仲美著作集』→今すぐ購入したい方はこちらへ |
|
|
『言葉から迫る平安文学1』
(源氏物語)
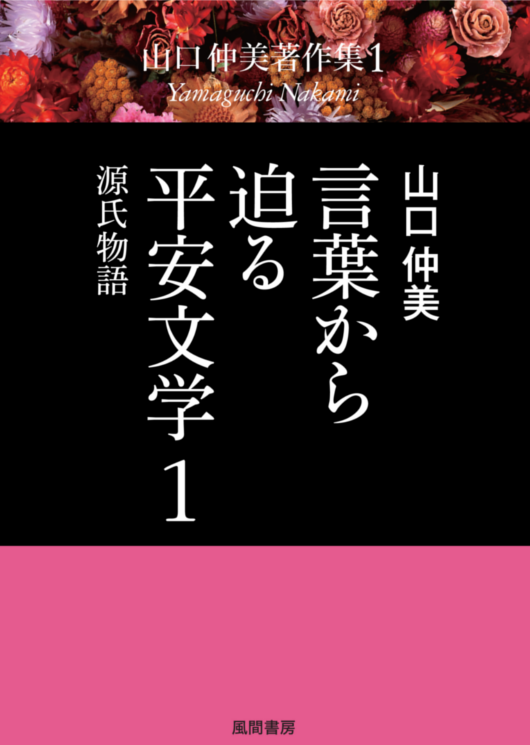
単著
山口仲美著作集1
|
2018年10月
風間書房 |
第一巻は、言葉や文体、そしてコミュニケーションといった言語学的な立場から、『源氏物語』のさまざまな問題を追究。三部から成る。
Ⅰ部は、「『源氏物語』男と女のコミュニケーション」。源氏物語に登場する男と女は、どんなコミュニケーションをとっていたのか? その様相を具体的に解明している。Ⅱ部は、「『源氏物語』の言葉と文体」。比喩や象徴詞(=オノマトペ)や形容語などに注目して、『源氏物語』独自の問題を解明する。Ⅲ部は、「文章・文体研究の軌跡と展望」。『言葉から迫る平安文学』1巻・2巻・3巻に共通する著者の立場を明確にしている。文章・文体研究の草創期の状態も明らかになる。
『山口仲美著作集』→今すぐ購入したい方はこちらへ
|
|
|
『趣味どきっ―恋する百人一首』

監修・執筆
|
2015年11月
NHK出版 |
小倉百人一首の恋歌を現代にも生きる「恋の処方箋」という観点からとらえたもの。第1回「ベッドイン」、第2回「許されざる恋」、第3回「キャリア系・清少納言の恋愛事情」、第4回「モテ女・和泉式部に学ぶ魔性テク大研究」、第5回「女の別れ道・セレブ美人妻・道綱母」、第6回「オクテな地味女・紫式部」、第7回「はじめよう!恋する心の伝え方」、第8回「恋の終わりの処方箋」といった内容に即して、百人一首の恋歌を取り上げていくものです。 |
|
|
『NHK「100分de名著」ブックス―清少納言 枕草子―』

単著 |
2015年 9月
NHK出版 |
NHK Eテレ『100分de名著』のテキストに、「女の才能、花開く」の一章を書き加えたもの。清少納言の『枕草子』を、紫式部『源氏物語』と和泉式部『和泉式部集』と比べてみると、その特質がより鮮明になります。
|
|
|
『擬音語・擬態語辞典』
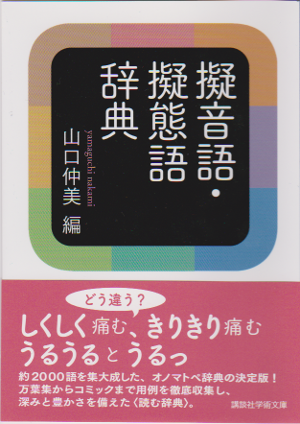
共著
|
平成27年5月
講談社 |
文化史から読み解く、読んで楽しい擬音語・擬態語辞典
『暮らしのことば 擬音・擬態語辞典』(講談社)が学術文庫となって新たに刊行されたもの。
全595頁
|
|
|
『NHK100分de名著―枕草子―』
第1巻43号
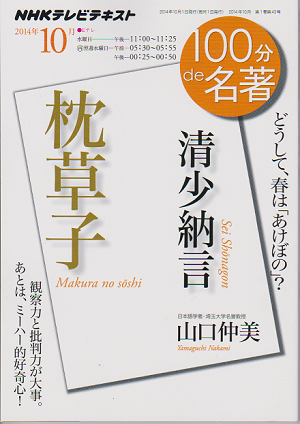
単著
|
平成26年10月
NHK出版 |
枕草子をマナー集として読んだ新しい試み
平成26年10月の毎水曜日にEテレで放映された「100分de名著」のテキスト版。枕草子の魅力を次の四点から述べたもの。(1)鮮烈な情景描写、(2)魅力的な男とは? 女とは? (3)マナーのない人、ある人 (4)エッセイストの条件。
全114頁
|
|
|
『大学教授がガンになって
わかったこと』
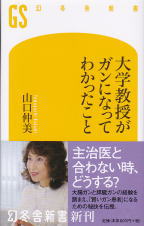
単著
|
平成26年3月
幻冬舎 |
賢いがん患者になるための秘訣
大腸ガンは、早期発見し、手術もうまくいったのだが四年後にすい臓がんを発症。自分の愚かながん患者体験を包み隠さずに書き記すことによって、読者に「賢いがん患者」になる秘訣を説いた本。
全252頁
|
|
|
『日本語の古典』
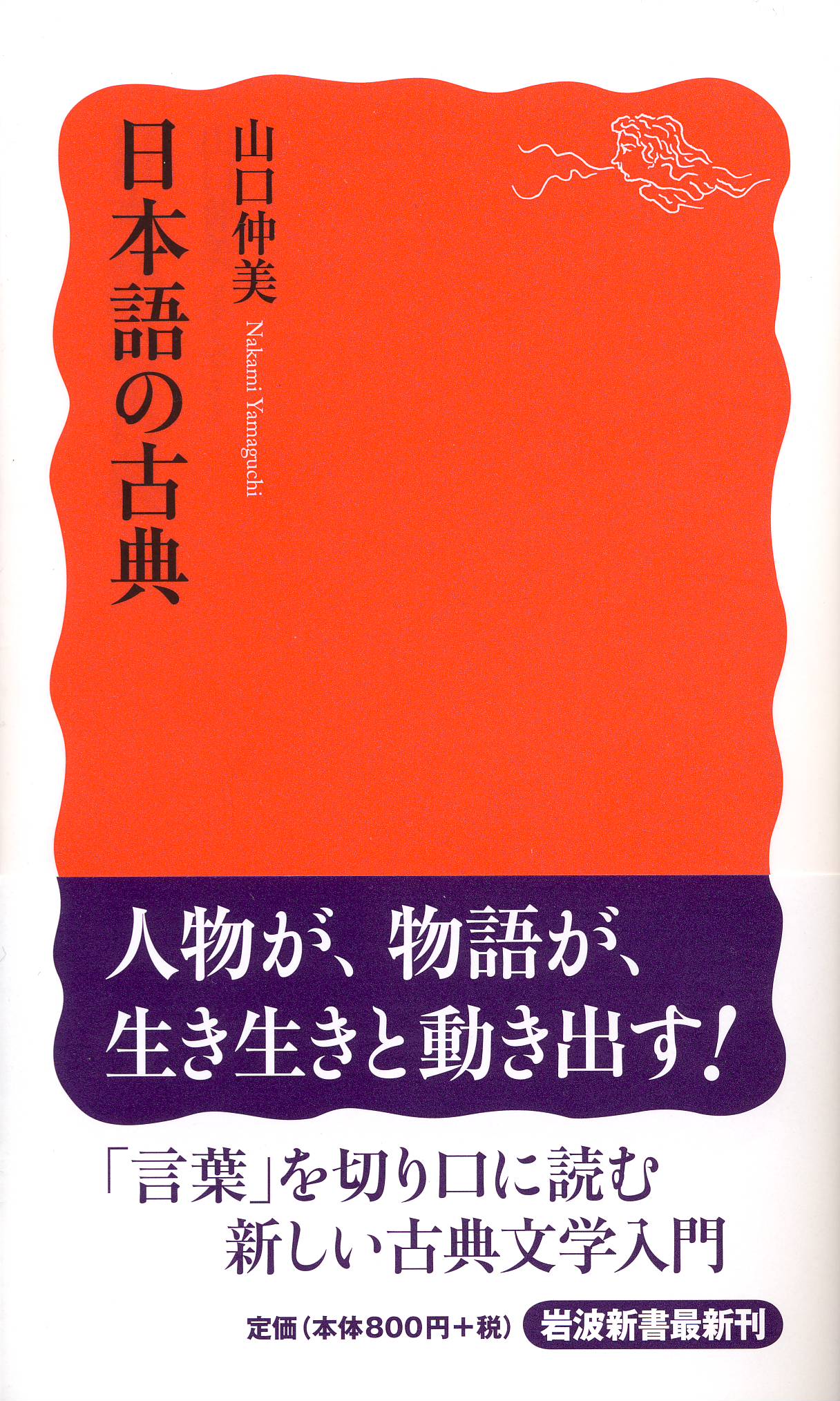
単著
|
平成23年1月
岩波書店 |
古典の苦手な方におススメです。
奈良時代の『古事記』から、江戸時代の『春色梅児誉美』、まで、歴代の名作三〇を取り上げ、作品ごとにテーマを設定し、言葉と表現からそれを読み解いた書。比喩、擬音語・擬態語、などを手がかりに、古典の底力、日本語の魅力の再発見をめざしたもの。
全248頁
|
|
|
『ちんちん千鳥のなく声は』
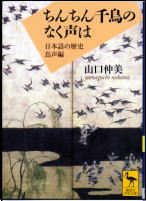
単著
|
平成20年11月
講談社 |
平成元年に出版された拙著『ちんちん千鳥のなく声は―日本人が聴いた鳥の声―』(大修館書店)をもとに、今回あらたに「鳥声索引」「事項索引」をつけ、利用しやすい形にして、新装版として学術文庫から出版したもの。鳥の写真なども、新しく入れ替えたものもあり、廉価で原本同様に楽しんでいただけると思う。
全317頁 |
|
|
『すらすら読める枕の草子』
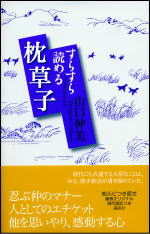
単著
|
平成20年6月
講談社 |
『枕草子』は、300近くの章段から成り立ったエッセイ集。この本では、そのうち「男と女のエチケット」「人としてのマナー」に関する章段を中心に採り上げて、見どころと解説を加えています。読み終わった後、「なんと現代にも役に立つ本なのか」と思ってもらえると確信しています。
全286頁 |
|
|
『新・にほんご紀行』
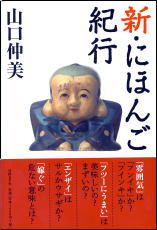
単著 |
平成20年3月
日経BP社 |
この本は3部仕立て。
第Ⅰ部は「テレビの言葉あれこれ」
これは日本経済新聞に「日本語チェック」として連載したコラムを集めたもの。採り上げた言葉はテレビに出てくる言葉で、今流行りの若者言葉から時代劇の言葉まで、あるいはドラマを象徴する言葉、笑いのネタ言葉と多種多様。
第Ⅱ部は「オノマトペに遊ぶ」
オノマトペというのは擬音語・擬態語のこと。「チントンシャン」「ヒャラリヒャラリコ」という楽器の音色はどこから来たのか?「ちんちんかもかも」「鶴の一声」はどこから生まれて来た表現なのか?あまり問題にされてこなかったテーマで書いた、オノマトペ関係の文章。
第Ⅲ部は「日本語の風景」
これは日本語に関する私の思いを述べた記事を集めたもの。敬語をどう考えるべきなのか?国際化社会に合った日本語とはどういうものなのか?男と女のコミュニケーションは昔はどうだったのか?などの問題について、私の考えを述べてみたもの。
全367頁
|
|
|
『若者言葉に耳をすませば』
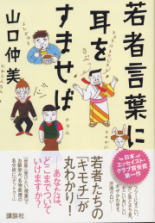
単著
|
平成19年7月
講談社 |
この本は、若者言葉とはどんな特色を持ち、どんな効果を期待して使われているのかということに焦点を絞り込んで、若者言葉を追究したもの。なぜ、どうして、という謎解きにできるかぎり挑戦してみた。また、若者たちとの座談会・中高年との座談会も織り込んで、それぞれの生の声を聞くことにも力を注いだ。読み終えたときに「なるほど」と思ってもらえる本にしたい。若者言葉がよく分かったと思える本にしたい。こうして書いたのが、この本。
全286頁
|
|
|
『「擬音語・擬態語」使い分け帳』

共著
|
平成18年11月
山海堂 |
愛の告白は「どきどき」した? 「はらはら」した? 私たちは、「わくわく」したり、「どきどき」したり、「いらいら」したり、「むかむか」したり。分かっているようで実はうまく説明できない「擬音語」「擬態語」の使い分けを明らかにした本です。言語感覚を磨くのに最適な本です。
全183頁
|
|
|
『日本語の歴史』

単著
|
平成18年5月
岩波書店 |
日本語の歴史を知るということは、日本語の将来を考え、日本語によってつむぎ出された文化そのものを大事にし、後世に伝えていく精神を培っていくのに役立ちます。でも、日本語の歴史を知りたいと思っても、一般向けに分かりやすく面白く書かれた本が、残念ながら、今のところ出ていません。一般の人に興味を持ってもらえる形で、日本語の歴史を語りたい。これが、この本を執筆した意図です。読んでいただくと、頭の中に実にすんなりと「あなたの使っている日本語」の歴史が見えてきます。
全230頁。
|
|
|
『すらすら読める今昔物語集』
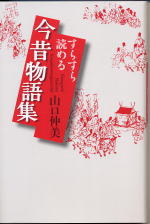
単著
|
平成16年12月
講談社 |
今を遡ること、九〇〇年前の日本の古典『今昔物語集』から、元気の出る話を選んで、その魅力を解説した書。大き目サイズの本文、その現代語訳、その話の見所が話ごとに付してある。古典なんて、大嫌いという方に是非ともお勧めしたい一書。
全245頁。
|
|
|
『中国の蝉は何と鳴く?』
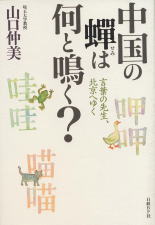
単著
|
平成16年11月
日経BP社 |
日本の古典文学や日本語が、中国人にどんなふうに学ばれ、受け入れられているのか?そんなことを中心に綴ったエッセイ。ウィットに富む中国人の会話、ユニークで忘れがたい中国人などについても記した痛快情報満載の中国滞在記。
全207頁。
|
|
|
『暮らしのことば 擬音・擬態語辞典』
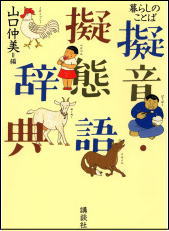
編著
|
平成15年11月
講談社 |
擬音語・擬態語は、日本語の特色になっている言葉。でも、意外に解説されることのない言葉。「しくしく」と「きりきり」はどう違うのか?「べろんべろん」と「ぐでんぐでん」は? こうした語の意味の違いの解説から、知られることのなかった文化史まで明らかにしてある辞典です。短歌や俳句、童話や小説、広告、詩など創作したい時にも役立ちます。 |
|
|
『よくわかる慣用句』
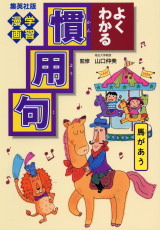
監修
|
平成15年11月
集英社 |
小学生の高学年から中学生向きに、慣用句をやさしく分かりやすく解説した書。「馬があう」「顔に泥をぬる」「あげ足をとる」など日常よく使う慣用句115句を取り上げて解説。言葉の面白さを感じてもらえる書物。 |
|
|
『よくわかる百人一首』
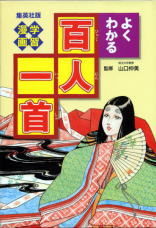
監修
|
平成14年12月
集英社 |
小学生の高学年から中学生向きに、百人一首をやさしく解説した書。お正月に向けての必須読本。 |
|
|
『犬は「びよ」と鳴いていた』

単著 |
平成14年 8月
光文社 |
擬音語・擬態語についてさまざまな面からのアプローチ。目次は次のとおり。
第一部・擬音語・擬態語の不思議
(1)擬音語・擬態語に魅せられる
(2)擬音語・擬態語のかたち
(3)擬音語・擬態語の寿命
(4)擬音語・擬態語の変化
(5)掛詞で楽しむ擬音語・擬態語
(6)辞典の中の擬音語・擬態語
第二部・動物の声の不思議
(1)昔の犬は何と鳴く
(2)ニャンとせう-猫-
(3)チウきころしてやらう-鼠-
(4)モウモウぎうの音も出ませぬ-牛-
(5)イヒヒンヒンと笑うて別れぬ-馬-
(6)われは狐ぢゃこんこんくゎいくゎい
(7)ももんがの鳴きやうを知らぬ
(8)美し佳しと鳴く蝉は-ツクツクボウシ-
全272頁。
|
|
|
『よくわかる俳句』
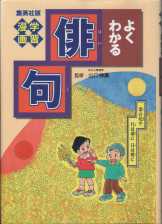
監修
|
平成12年 1月
集英社 |
小学生の高学年から中学生向きに、俳句をやさしく解説した書。全国学校図書館協議会選定図書・日本子供の本研究会選定図書となる。 |
|
|
『よくわかる四字熟語』
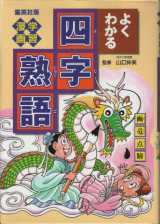
監修
|
平成12年 1月
集英社 |
小学生の高学年から中学生向きに、四字熟語をやさしく解説した書。全国学校図書館協議会選定図書・日本子供の本研究会選定図書となる。 |
|
|
『よくわかることわざ』
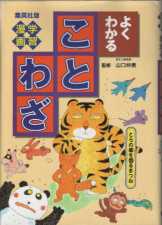
監修
|
平成12年 1月
集英社 |
小学生の高学年から中学生向きに、ことわざをやさしく解説した書。全国学校図書館協議会選定図書・日本子供の本研究会選定図書となる。 |
|
|
『平安朝の言葉と文体』

単著 |
平成10年 6月
風間書房 |
これまでに書いてきた平安文学作品の語彙・単語の意味・表現・文体についての論文をもとに、加筆修正を加え、さらに新たに「『源氏物語』の女性語」「『源氏物語』の雅語・卑俗語」「『源氏物語』の漢語」などの語彙の三論文を書き加えて、一書としたもの。次の五部構成からなる。
序編「和文体の歴史」、第一部「物語の言葉と文体」、第二部「日記の言葉と文体」、第三部「説話文学の言葉と文体」、付編「感覚・感情語彙の歴史」。
さらに、第一部から第三部までは、それぞれ十一章、四章、五章で構成されている。
全431頁。
|
|
|
『言葉の探検』

単著
|
平成 9年11月
小学館 |
従来余り取り上げられていない言葉、たとえば、「嫉妬」「男する」「赤裸」「愛敬」「太っ腹」「したり顔」などの語に注目して、その言葉の意外な側面を明らかにすることを目的にした書。次の八章からなる。第一章「言葉の探検」、第二章「読み・書きの話」、第三章「言葉の変遷・語源」、第四章「効果的な言葉遣い」、第五章「失敗した言葉遣い」、第六章「名づけの話」、第七章「古典語の話」、第八章「若者言葉・熟年言葉」。
全187頁。
|
|
|
『源氏物語を楽しむ』

単著
|
平成 9年 7月
丸善株式会社 |
『源氏物語』の主人公、光源氏は、恋や結婚の場で、女性たちとどんな駆け引きのある会話を交わしているのかを解明してみようとした書。光源氏の相手になった女性たちは、人柄や環境に応じて個性豊かな言葉を発し、彼とさまざまな関係をつくっていく。言葉によって紡ぎ出されていく人間関係を『源氏物語』を例に追究した書。
全204頁。 |
|
|
『たのしいネーミング百科』
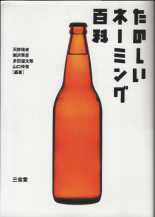
共著 |
平成 7年12月
三省堂 |
天野祐吉・関沢英彦・多田道太郎・山口仲美の四人による座談形式の著書。江戸時代から、現代に至るまでのネーミングに関する様々なテーマをそれぞれの切り口から論じたもの。第一章江戸期、第二章明治前期、第三章明治後期、第四章大正ひとけた、第五章大正ふたけた、第六章昭和ひとけた、第七章昭和十年代、第八章昭和二十年代、第九章昭和三十年代、第十章昭和四十年代の十章からなる。
全254頁。
(同書は、さらに平成12年5月学陽出版社から、学陽文庫『楽しいネーミング百科』として刊行された。)
|
|
|
『平安朝'元気印'列伝―今昔物語の女たち―』

単著 |
平成 4年12月
丸善株式会社 |
平安末期の『今昔物語集』から、たくましい女性たちを描いた説話を取り上げ、その表現方法を解き明かしていった書。たとえば、本書の第一章「あらぬ女をくどいた話」では、『今昔物語集』巻28第1話をとりあげ、敬語と卑罵語の現れ方に注目し、それらの語によっていかに女性の怒りが効果的に表現されているかを明らかにした。以下の章でも、順次、ドライな性描写の方法、語り口を髣髴とさせる独特な表現方法、ビジュアルに事件を表現する方法、擬音語の巧みな使用法、事件を謎めかす描写方法、起承転結によるスピーディな文章構成法、動作によって心理を描き出す方法、漸層法というレトリックを駆使して読者を引きつけていく方法を具体的に解明していった。
全224頁。
|
|
|
『恋のかけひき―源氏物語もうひとつの読み方―』

単著
|
平成 3年 6月
主婦と生活社 |
『源氏物語』を、男女の会話から読むことによって、その表現の魅力を解き明かそうとした論。コミュニケーション論の立場からする新しい読みの試みである。本書は、三部から成り、第一部は、光源氏と彼をめぐる女性たちとの会話、第二部は、夕霧と彼をめぐる女性たちとの会話、第三部は、薫・匂宮と彼らをめぐる女性たちとの会話を対象に分析した。
その結果、従来の解釈で納得できない問題点と新しい解釈、従来余り気づかれていない登場人物の性格などが解明されてきた。全238頁。
|
|
|
『ちんちん千鳥のなく声は―日本人が聴いた鳥の声―』
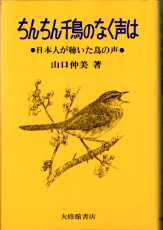
単著 |
平成 1年 4月
大修館書店 |
鳥の声を写す言葉(=擬声語)の歴史を、日本人の意識や環境に絡めながら、解明した書。次のような章立てで記述している。(1)はじめに、(2)嬶(かかあ)嬶(かかあ)とよびわたる-カラス、(3)ほほうほほうもほめことば-ウグイス、(4)仏壇に本尊かけたか-ホトトギス、(5)ひいる盗人とさけべば-トビ、(6)虚空にしばしひひめいたり-ヌエ、(7)お口をそろえてちいぱっぱ-スズメ、(8)糊すりおけとよぶ声に-フクロウ、(9)妻恋う声はけんけんほろろ-キジ、(10)ちんちん千鳥のなく声は-チドリ、(11)うたう声にも血の涙-ウトウ、(12)がんがんがんと鐘ならせ-ガン、(13)こけこっこのおばさんに-ニワトリ、(14)おわりに。
全269頁。
なお、本書の一章である、ウグイスの声の歴史は、『歴史読本』39巻24号に転載された。
|
|
|
『生きていることば』
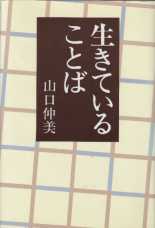
単著
|
昭和62年11月
講談社 |
現代使っている言葉の中から、(1)書き誤られやすい言葉、(2)読み誤られやすい言葉、(3)意味の取り違えられやすい言葉、(4)語源のわからなくなりつつある言葉、(5)使いあやまられやすい言葉の例を、それぞれ具体的に取り上げ、その史的推移を明らかにしながら、言葉の問題を分かりやすい形で述べた書。
全284頁。 |
|
|
『明治期専門術語集』
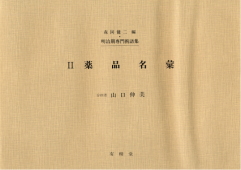
共著 |
昭和60年 3月
昭和59年度文部省科学研究費補助金による出版 |
代表者・林大、分担者・森岡健二・高野繁男・山口仲美・日向敏彦・松岡洸司・塩沢和子の六人。
明治期専門術語集『医語類聚』『薬品名彙』『物理学術語和英仏独対訳字書』『工学字彙』『数学ニ用ヰル辞ノ英和対訳字書』『鉱物字彙』の解説をし、そこに用いられている術語の語構成を調査報告した書。
山口仲美が担当したのは、第二分冊の『薬品名彙』である。
なお、本書は、昭和60年9月に有精堂からも刊行された。
|
|
|
『命名の言語学―ネーミングの諸相―』
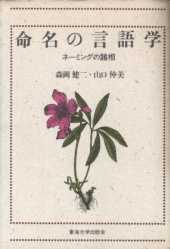
共著 |
昭和60年 3月
東海大学出版会 |
森岡健二と山口仲美の二人による共著。命名の仕組みとその実態の解明を意図した書。次の二部から構成されている。
第一部「名と名づけ」、第二部「名づけの種々相」。山口仲美が執筆したのは、第二部の176頁分である。
執筆した第二部は、次の四章からなっている。第一章「名づけの苦しみ―学術用語名―」、第二章「名づけの楽しみ―あだ名―」、第三章「名づけの志向―売薬名(上)―」、第四章「名づけの志向―売薬名(下)―」
全299頁。
|
|
|
『平安文学の文体の研究』

単著 |
昭和59年2月
明治書院 |
『源氏物語』『今昔物語集』をはじめとする平安文学作品を対象にして、作品の個的な文章特性の解明を意図した書。追究方法は、擬声語・擬態語(=象徴詞)、形容詞・形容動詞、比喩表現、心情表現、文末表現、朧化表現など、個性を明らかにすることの見込まれる言語表現を、作品ごとに探索しては、調査項目に設定しつつ行なった。いわば、文体論の方法を模索しながら、古典における文体研究の確立を目指した書である。
本書は、次の四部構成からなる。第一部「文体研究への展望」、第二部「比喩と文体」、第三部「象徴詞と文体」、第四部「作品の性格と文体的特性」。それぞれの部は、さらに四章ないし六章から構成されている。全566頁。
なお、本書は、「第12回金田一京助博士記念賞」を受けた。 |
|
|
『文章・文体 論集日本語研究』

単著
|
昭和54年 4月
有精堂 |
文体理論・現代文の文体研究に関する論文を編集し、解説をほどこした書。全体を(1)文章論、(2)文体論、(3)表現論、(4)文章作法の四分野に分かち、従来発表された先人の卓論を紹介することを目的とした書。研究文献目録も付す。 |
|
|
『今昔物語文節索引・巻四』

共著
|
昭和54年 2月
笠間書院 |
馬淵和夫監修、山口佳紀・山口仲美編。下坂勝洋・馬淵昌子校書。『今昔物語集』巻四の文節索引。 |
|
|
『今昔物語文節索引・巻五』

共著
|
昭和48年10月
笠間書院 |
馬淵和夫監修、山口佳紀・山口仲美編。『今昔物語集』巻五の文節索引。 |
|
|
|
|
|
|
 |
 |
 |