 |
|
 |
|
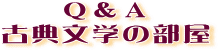
| Q. |
『源氏物語』は、「光源氏」という一人の男性を中心に、たくさんの女性との恋愛や結婚が描かれています。現代では許せないと言う気がしますが…(10/8更新) |
| A. |
それは、平安時代の貴族の結婚形態を考えてあげないとかわいそうです。上流貴族社会では、男性は、「正妻」の他に、複数の「妾妻」を持つことが許されていました。当時の結婚形態については、よく「一夫多妻制」といわれています。ところが、最近の研究成果(工藤重矩『平安期の結婚制度と文学』風間書房 1994年2月刊)によって、それが、誤解を生みやすい言葉であることが分かってきました。一人の男性が、同時に多数の妻を持つことが出来るわけではないからです。
当時においても、一人の男性が法律上結婚できるのは、一人の女性に限られています。家同士の話し合いがなされ、親族に認められた結婚を行い、法律的にも社会的にも認められている妻は、ただ一人なのです。「嫡妻(正妻)」と呼びます。
ただ、現代と違って、当時の男性は、「正妻」の他に、複数の「妾妻」を持つことが、社会的に許容されていたのです。「妾妻」は、法律的には、認められていませんから、男性の愛情が薄れれば、割合簡単に関係が解消されてしまう不安定な存在です。
また、複数の「妾妻」たちの間には、出自や、男性の愛情の度合いによって、序列が出来ています。男性からの経済的な援助も、それぞれ分に応じて受けることが出来たようです。
「正妻」の他に、複数の「妾妻」を持つことが、社会的に承認されていることが、多様な恋物語の温床となったのです。
さらに、現在とは違った点として、「召人」の存在があげられます。男性の身分が、極めて高く、女性の身分が低い場合には、いくら愛し合っても、女性は、「妾妻」にも数えられず、単なる「召人」として男性の邸宅に引き取られ住み込む以外にはないといった場合があります。
このほか、「妾妻」「召人」にもならずに、世間に公表されることのない密やかな「愛人」関係を続ける女性たちもいます。
『源氏物語』に登場する女性たちは、「正妻」か「妾妻」か「召人」か「愛人」かといった格付けを持っています。たとえば、「葵の上」は、光源氏の「正妻」です。彼女の敵視した女性「六条御息所」は、光源氏の「愛人」格にとどまりました。光源氏が、彼女との関係を秘して、世に公表しませんでしたから。正妻「葵の上」は、長男の「夕霧」を出産した直後に亡くなってしまいました。彼女の亡き後、光源氏は、晩年に至るまで「正妻」をもうけません。「紫の上」という最愛の「妾妻」がいたからです。
「紫の上」は、正妻と同じように大事にされ、最高の待遇を受けていますが、法律上は「正妻」ではなく、「妾妻」の一人に過ぎません。だからこそ、光源氏の愛を失わないために努力し賢明に生きる、理想的な女性であり続けたのです。
光源氏は、晩年になって皇女「女三の宮」を「正妻」として迎え、ために苦悩の種を背負い込み、人生が暗転して行きます。
『源氏物語』を、当時の結婚形態を頭に置いて読んでみると、女の深い悩みが見えてきますよ。
(以上は、山口仲美『源氏物語を楽しむ─恋のかけひき─』丸善ライブラリー¥660をもとに答えを作成しています。)
|
|
|
|
 |
 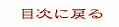 |
 |
|