 |
|
 |
|
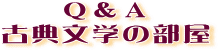
| Q. |
『竹取物語』は、『源氏物語』と同じ平安文学作品なのに、なぜあんなに違った印象がするのですか?
(11/4更新) |
| A. |
それは、『竹取物語』の言葉に、その原因の一つがあります。『竹取物語』には、びっくりするような荒々しく野蛮な言葉がたくさん出てきます。竹の中から、光輝くようにして生まれたかぐや姫が、多くの求婚者を退けて、月の都に帰っていくといった幻想的な筋立てなのに、です。
ご存知のように、かぐや姫に積極的にプロポーズしたのは、五人の貴公子と天皇。五人の貴公子は、それぞれかぐや姫から難題を出されます。そのうち四番目の大伴大納言は、かぐや姫に「龍の首にある五色に光る玉を取ってくれば、あなたのお嫁さんになるわ」と言われました。
彼は、かぐや姫に夢中なので、家来たちにまかせておくことが出来ずに、自らそれを求めて家を出ました。海に来ると、船頭一人をやとって、舟にのり込み、広い海原にこぎ出しました。けれど、途中で大時化にあって船は難破寸前。死に怯え泣いている船頭を見て、大納言は『青反吐をつきて』おっしゃった。「船に乗ったら船頭だけが頼りなんだ。しっかりしろ」と。
さすが気の強い大納言です。自分も船酔いで「青反吐」を吐いているのに、船頭を叱咤激励しています。ただのヘドでも汚いのに、さらに「青」をつけて強調した「青ヘド」です。こんな言葉は、『伊勢物語』『宇津保物語』『源氏物語』などの王朝文学に見られるはずがありません。平安末期の『今昔物語集』は、この手の言葉を平気で使う作品ですが、それでも「ヘドをつく」とは出てきません。もう少し婉曲に「物をつく」「物つく」と言っています。「ヘド」と言わずに「物」と言ってぼやかしているのです。『竹取物語』が、かなり凄い言葉を使うことが分かりますでしょう?
それにしても、「ヘド」という言葉は、もう平安時代の初めにはあったんですね。その頃の辞書にも「嘔吐 ヘドツク」(『和名類聚抄』)と出てきます。ヘドは、「吐く」ものではなく、古くは「突く」ものだったことが分かります。「唾」は「吐く」と言っています。「つく」は、吐き出すの意味です。
現在でも「溜息をつく」といいますが、あの「つく」が、ヘドにも用いられていたわけです。
また、かぐや姫にプロポーズした五番目の男性は、石上 中納言です。彼は、かぐや姫に、「燕の巣にあるという子安貝を見つけてもってきたら結婚するわ」と言われました。子安貝っていうのは、安産のお守りになる貝です。
彼も、かぐや姫に熱中しています。燕が子を産むときに出すという子安貝を求めて、自ら篭にのって燕の巣までのぼって、探りました。すると、手にひらべったいものが触れました。中納言は大喜び。これこそ、子安貝に違いない。下で篭をつりあげている家来たちに向かって叫びました。
「わしは、子安貝らしいものを握ったぞ。さあ、みんな綱をゆるめておろしてくれ。」
家来たちは一刻も早く下に降ろそうとあせって、綱を緩めるだけではもどかしく、反対側からもひっぱったので、綱が無くなり、その瞬間、中納言は、下にあった鼎
の上にまっさかさまに落ちてしまいました。中納言は、白眼をむいて、虫の息。それでも、中納言は、子安貝の顔を見ようと灯をもってこさせました。だが、手をひろげてよく見みると、『つばくらめのまり置ける古糞をにぎりたまへるなりけり』。
燕がたらしておいた古糞を握っていらっしゃたのです。「まり置ける」の「まり」は、動詞「まる」の連用形。「まる」は、大小便をする、排泄するという意味の言葉です。『伊勢物語』『宇津保物語』『源氏物語』『枕草子』といった文学作品には、もちろんこんな言葉は出てきません。卑俗な言葉を厭わない『落窪物語』にも、見られません。かろうじて『今昔物語集』には、「糞まる」という形で出てきます。女の子が、大路にしゃがんで「糞まり」ていると出てきます。
今でも、赤ちゃんが用を足す便器のことを、「おまる」といいますが、「まる」は、排泄するの意味の古いことばです。中納言の握っていたのは、子安貝ではなく、燕の排泄した古糞だったんですね。
「糞」という言葉も、『源氏物語』をはじめとする優美な王朝文学作品には見られません。『落窪物語』や『今昔物語集』などの俗語好きの作品にのみ見られます。そこでも「糞」であり、「古糞」ではありません。
でも、『竹取物語』は、言葉に異常な興味を持っておりまして、よくずっこけた語源解釈のオチが付いています。この石上中納言の話でも、中納言は、自分の握っていたのが、貝ではなく、燕の糞だと分かると、「ああ、貝がないことだ」とおっしゃった。ここから、やっただけの効果がないことを「甲斐なし」というようになったんだね、なんてまことしやかに述べたてているんです。「甲斐なし」の「甲斐」は宛字ですが、「交ひ」からきたものです。ある行為の引き換えに得られる効果を意味します。『竹取物語』って、語呂合わせのような語源解釈を随所で披露しています。おちゃめでしょう?
(以上の答えは、山口仲美著『言葉の探検』小学館 の内容を元に構成しています。)
|
|
|
|
 |
 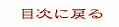 |
 |
|