 |
|
 |
|
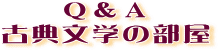
| Q. |
古典が好きになるにはどうしたらいいでしょうか?(3/21更新) |
| A. |
私が古典が好きになった理由をお話して参考にしていただきましょうか。
私は、現在古典の文章の魅力や言葉の研究をしているのですが、なぜ古典が好きになったのか? 考えてみますと、学校の国語の授業で熱心な国語の先生に出会い、面白い古典に次々に触れていったことがきっかけとなっています。 中学では、私たちの国語の先生は病気がちで、授業は自習が大半でした。ですから、ほとんど先生から教えていただいた記憶はありません。中学の教科書には古典が少し載っていましたけれど、一人で読むほど熱心ではありませんでした。
高校生になって、私は、迫力満点の教え方のうまい国語の先生に出会いました。先生は、古典の時間に、短編でストーリー性のある話や、はっと目を見開くような話をプリントしてきては読んでくれたのです。それらの作品を思い浮かべてみると、『伊勢物語』『大和物語』『堤中納言物語』『徒然草』『枕草子』などです。別に作品そのものが目新しいわけではなく、多くは国語の教科書に出てくるものです。
その先生のユニークな点は、教科書に出ていない箇所で生徒の興味を引きそうな話を選び、プリントしてきては我々に配布し、読んでくれたことなのです。平易な文章からなる短い話ばかりなので、先生の現代語訳を聞きながら、原文を辿ることは難しくはありません。
先生が教材に選んでくる話というのは、たとえば、『伊勢物語』なら、六十五段の文章。高貴な女性に思いをかけ、許されぬ恋ゆえに男は女を忘れようと神にまで祈るのですが、忘れられず遂に男も女も身を滅ぼすという話。激しく恋する男の心、理性ではいけないと分かっているのに情にほだされる女の心が、思春期にある私たち高校生の心を捉え、古典の時間に新鮮な体験をしました。
『大和物語』なら、一四五段の文章。経済的に行き詰まった夫婦が、夫の提案で別れて別々の人生を歩むことになります。妻は都に上る。運が付いて高貴な人の後妻になりました。ですが、元の夫のことが気にかかる。寺参りという名目で、もと住んでいた難波に妻はやってきました。付き人も大勢従えています。そこで目にしたのは、乞食のように落ちぶれた元の夫の姿でした。妻は、胸が張り裂けそうに悲しく、こっそりと物を与えようとしたところ、男の方も女が元の妻であることに気づきます。男は、自分のふがいなさを恥じ、歌を書き付けて、姿をくらましてしまったという話。人生の不思議さを感じた文章でした。
『堤中納言物語』の「虫めづる姫君」も、印象的な作品でした。短編とはいえ、藁半紙三枚にぎっしりガリ版刷りされた原文には、先生の熱意が込められていました。当時はコピーなんてありませんから、先生がせっせとガリ版に書いて黄色くてざらざらな藁半紙に印刷してくれていました。手作り教材から先生の熱い心が伝わってきました。先生の作った古典教材を眺め、先生の大音声の現代語訳について行くと、まずは、蝶よりも、毛虫が好きだという女性の登場に、度肝を抜かれました。さらに、彼女の毛虫を愛する理由に驚きました。
「人々の、花、蝶やとめづるこそ、はかなくあやしけれ。人は、まことあり、本地たづねたるこそ、心ばへをかしけれ。(=人々が、花や蝶をもてはやすのこそ、あさはかです。人間というものは、誠実な心があって、もとの姿を追究してこそ奥ゆかしいのです)」。
すごいことを言いいます。自分たちと同じくらいの年齢の女性に違いないのに、彼女の真実を見抜く目の確かさに圧倒されました。そんな女性が、平安時代にいたのです。彼女は、その後も長く私の胸に住み続け、折に触れては顔を覗かせました。
同じ物語の中にある「はいずみ」という短編も、プリントしてくれました。突然やってきた男に慌てふためいて、白粉と間違えて黒いまゆずみ眉墨を顔に塗りたくって「目のきろきろとして(=目ばかりきらきらぱちくりとして)」男の前に出てしまった女。あまりの不気味な顔に卒倒せんばかりになって、女のもとを辞する男。結局二人の中は壊れてしまい、男は元の妻のもとに帰って一件落着。妙にリアリティのある話でした。
『徒然草』『枕草子』からは、美しいというのはどういうことか、生きるということはどういうことかを教えてくれる章段を読んでいきました。私たちのクラスの大半は、一年経つうちに、古典好きになっていました。分かりやすい文章で書かれ、ストーリー性や訴えかけのある短編を次々に与え続けていった先生の勝利です。
古典なんか、一人では読みません。だから授業で面白い作品に触れさせるのが、最も効果的な方法の一つです。こと古典に関しては、国語教師の役割は極めて大きいと私の経験は語っています。
(上の原稿は、「古典が好きになったわけ」『国語教育相談室』27号、2000年2月に基づいて加筆してあります。) |
|
|
|
 |
 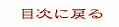 |
 |
|