 |
|
 |
|
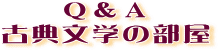
| Q. |
『源氏物語』の主人公・光源氏が、最も魅力的と思われるのは、どんな点ですか?(4/29更新) |
| A. |
光源氏がとりわけ魅力的なるのは、若い女性女三宮との結婚に失敗した後です。では、以下具体的に述べて見ましょう。
1 ほかに妻などいらなかった
紫の上の心を失ってまで決行した光源氏の晩年の女三の宮との結婚は、うまく行ったであろうか?
紫の上の孤独感については、言うまでもあるまい。だが、光源氏も孤独になり、紫の上とは全く異質の苦悩に満ちた人生を歩んでいた。その姿は、それまでの理想的な光源氏像を打ち破り、人間の匂いを発散している。
女三宮との夫婦生活を簡略に追いながら、それまでとは違った光源氏の人間的な魅力を明らかにしておきたい。
華々しく輿入れしてきた女三の宮は、妻と呼ぶにはあまりにもあどけなく幼かった。光源氏は、がっかりして後悔した。
「どのような事情があるにせよ、どうして他に妻を迎えることがあろうか。浮気っぽく、気弱になっていた自分の気持ちのゆるみからこのような事態にもなってくるのだ」 (などて、よろづの事ありとも、また人を並べて見るべきぞ。あだあだしく心弱くなりおきにけるわが怠りに、かかる事も出で来るぞかし)
光源氏の呻き声が聞こえてきそうな心中思惟の言葉である。だが、事態は、もう取り返しがつかない方向に流れ始めている。女三の宮への期待はずれと紫の上への申し訳なさに光源氏は責めたてられ、後悔は苦悩に進んでいった。
しかし、光源氏は体面を重んじる人である。大変な人を正妻に迎えてしまったと思いながらも、外に対してはやはり女三の宮を自分の選んだ正夫人として大切に扱うことを忘れなかった。にもかかわらず、事もあろうに、彼が紫の上の病気の看病に明け暮れている時、女三の宮は、柏木という太政大臣の長男と情を交わしてしまったのである。密通は露見しない限りは、闇から闇に葬り去られる。しかし、柏木と女三の宮の密通は、光源氏が最も苦しむ方向で顕現した。
2 見てしまった手紙
光源氏は紫の上のところにいたが、女三の宮の妊娠を知らされてやってきた。腑に落ちない思いがある。久しく女三の宮を抱いていないのだ。女らしくなった女三の宮のもとに、その晩は泊まった。朝早く光源氏は、紫の上のところに帰ろうとして身支度を整えている時、ふと目に留まったものがある。緑の薄様の手紙である。女三の宮は、まだ寝ている。
何気なく手に取ってみると、「男の手なりけり」。読んでみると、「まぎるるかたなく、その人の手なりけり」。柏木なのだ。情を交わしたことが歴然とした書きぶり。不用心なと光源氏は思う。女に出す手紙は、落ち散って人手に渡る恐れもあるのだから、相手の女性にだけ分かれば良いようにぼかして書くものだと、恋の道のベテランの光源氏は心中で批判する。女三の宮自ら進んでではないことは分かるが、その幼さに舌打ちされる。
男が、女房の手引きで寝室に忍び込んできても、本人が近寄りがたく毅然とした態度をとり続ければ、男も手出しが出来ないものである。藤壷や空蝉は立派だった。寝室に入り込んだ光源氏を見事なやり方ではねつけたではないか。女三の宮には、それが出来なかった。自ら機転を利かせて、物事を処理する力がなかった。ひたすら甘やかされて育った頼りなく幼い姫君なのである。
光源氏は、女三の宮のみごもった子が柏木の子であることを知ってしまった。偶然、動かし得ない証拠を手にしてしまった時、あなたが夫なら、どうするであろうか? ことを公にして離婚するであろうか?
光源氏は、そうしなかった。彼は、相手のこと、自分のことをじっくり考えて、正妻の密通を、自分の胸の内にだけとどめる決意をした。事実が明るみに出たときに、深傷をおうのは、女三の宮の方であることを考慮したのであろう。女三の宮は皇女なのだ。皇女の不倫として大スキャンダルになってしまうであろう。それに対して、光源氏の方は、女三の宮への監督不行届の非難を浴びるであろうし、また妻を寝取られた間抜けな男として道化の役を引き受けねばならないであろう。しかし、女三の宮よりは傷が浅いのである。
光源氏は、紫の上にもこのことを漏らさなかった。危篤状態を脱し小康状態を保っている紫の上に話せば、少しは精神的に楽になったかもしれないのに、光源氏は、ぐっとこらえた。恐らく、全てもとを正せば、自分の心の奥底に潜んでいた浮気心が原因であることを自覚し、深く反省していたからであろう。
自分で蒔いた種は、自分で刈り取らねばならない。光源氏は、そう覚悟していたに違いない。泣き言を漏らさずに自分一人で責任をとって処理していこうとする光源氏の姿には、成熟した中年男性の魅力がある。
3 まさかと思うことがおありでも
誰にも言えない苦しみを胸に抱いて、光源氏は頭を抱える。と、若かりし頃、彼が継母の藤壷と密通して子をなしたことが脳裡を去来する。それは誰にも知られずに終わり、皇子は父帝の子として育てられ天皇になった。今度の事件はその天罰のようにも思えてくる。父帝は、自分たちのことを察知していたのであろうか? 何も言わずにそしらぬふりをしていただけなのかもしれない。今さらながら、彼は亡き父の目を感じ、罪の意識におののく。そして、女三の宮と柏木を許そうと思う。
だが、妊娠している女三の宮と二人きりになると、彼は、忍耐の緒が切れて、柏木のことをほのめかして脅してしまう。
「まさかと思うことがおありでも、粗略なお扱いだと人に見とがめられるようなことはすまいと思っております」 (思はずに思ひきこゆる事ありとも、おろかに人の見とがむばかりはあらじとこそ思ひはべれ)
どんなことをあなたがしたとしても、正夫人の待遇を変えない。それが、院のご依頼にこたえる道だと光源氏は言っている。光源氏は、若い時から、一度その気になったら、最後まで相手を捨てるようなことをしない人なのだ。女三の宮は、ただ恥ずかしそうに顔をそむけている。
光源氏と女三の宮の間には、いわゆる大人どうしの男と女の会話は見られない。光源氏が、年の離れた女三の宮に一方的に話しかけたり教え諭したりする言葉が見られるだけである。
光源氏はなおも言い続ける。
「今では、すっかり年寄りになってしまった私の姿も、見くびってもう飽き飽きしたとご覧になっていられるらしいのも、あれもこれも残念にも情けなくも思われますが、院が御在世の間は、やはり我慢して、院が私を夫とお決めになったのはそれなりのお考えもあったのでしょうから、この老い人をも、同じようにお思いやり下さって、そうひどくお見下しなさいますな」 (今は、こよなくさだすぎにたるありさまも、あなづらはしく目馴れてのみ見なしたまふらむも、方々に口惜しくも、うれたくもおぼゆるを、院のおはしまさむほどは、なほ心をさめて、かの思しおきてたるやうありけむ、さだすぎ人をも、同じくなずらへきこえて、いたくな軽めたまひそ)
誰と「同じように」思えと言うのだろうか?
光源氏は口に出していないが、柏木を背後に匂わせているのであろう。自分を老人扱いし、極端に自己卑下することによって、強烈な嫌みと当て擦りをしている。せめてもの復讐である。かつて、光源氏は、同性に嫉妬したことがなかった。常に勝者だったからである。だが、今や妻を寝取られた老い人なのだ。
一人で考えている時は、女三の宮を許そうと思うにもかかわらず、本人を目の前にすると嫌みや当て擦りを言ってしまう光源氏。昔物語のヒーロー像を脱し、綺麗事では動かぬ人物として造型され、人間くささを発散して生きている。
光源氏は、最後に女三の宮にしんみりと言って聞かせる。
「今さらに、思いも寄らぬあなたのお噂をお父さまのお耳に入れてご心配をおかけするようなことはなさいますな」 (今さらに思はずなる御名漏り聞こえて、御心乱りたまふな)
父親にも柏木のことは言わないように、と女三の宮に取るべき態度を教えている。ここまで教えてやらねばならない相手なのである。女三の宮は、後から後から溢れ出る涙を抑えることが出来ない。柏木の件では、彼女も彼女なりに苦しんでいるのだ。
光源氏も、彼女の涙を見ながら、自分の過去の罪におののき、因果応報の思いに捕らわれ、涙にむせぶ。
4 誰しも老いは逃れられない
では、柏木に対して、光源氏はどのような態度をとったか? 柏木が例になく光源氏邸に顔を見せなくても放っておいた。柏木に迂闊者と思われているようで気後れがするし、会えば平静でいられるとも思えないのである。
だが、どうしても柏木を呼ばなければ周囲の人が疑念を抱くような音楽の催し物が光源氏邸で行われることになった。光源氏は、気持ちを抑えて、柏木を招待した。しかし、柏木は、重く病んでいる由を申してやって来ない。光源氏も、来ないのは悩んでいるのだろうかと気の毒になってわざわざ手紙をやる。こういう優しさが光源氏の持ち味でもある。柏木の父親も、大した病気ではないのだから、光源氏邸に参上するように勧める。柏木は、つらさを圧してやってきた。
柏木は、話しに聞いていたとおりすっかり痩せてしまって顔色が悪い。だが、光源氏は、柏木を目の前にすると許しがたい気持が沸き上がる。光源氏は、優しそうに装って、柏木に声をかける。
「拍子を調えられるのは、君しかいないんで、お越しを願ったよ」 (拍子ととのへむこと、また誰にかはと思ひめぐらしかねてなむ)
柏木は、恥ずかしさで顔色が変わっている。だが、柏木も動揺する心を抑えて、
「脚気というものがひどくおこりまして。…勤めも休んでおりまして」 (例もわづらひはべる乱り脚病といふものところせく起こりわづらひはべりて、…内裏などにも参らず)
などと言葉を選び選びして無難な答えをした。 宴もたけなわになった。光源氏は、沈鬱な顔でふさぎ込んでいる柏木に目を据えて、冗談めかして言ってのけた。
「よる年波につれて、酔えば泣けてくるという癖はどうにもとめられなくなってきましたよ。衛門の督が、目敏く見つけて、笑みを浮かべておられるのは、なんとも恥ずかしいことですな。なに、それでも、その若さも今しばらくのことですよ。年月は、逆さまには流れぬもの。誰しも老いは逃れられない」 (過ぐる齢にそへては、酔ひ泣きこそとどめがたきわざなりけれ。衛門の督心とどめてほほ笑まるる、いと心恥づかしや。さりとも、いましばしならむ。さかさまに行かぬ年月よ。老いは、えのがれぬわざなり)
衛門の督は、柏木の官職名。光源氏の目は、柏木を射るような光線を発している。柏木が笑っているはずがないではないか。だが、光源氏は、老人の私を馬鹿にしたなと一矢報いなければ気がすまない。おまけに若さも瞬時のことだと痛烈な皮肉を言わずにはいられない。光源氏が、最も人間的な嫉妬の情をあらわにしている。
柏木は、座にいたたまれずに途中で退席したが、家に着くなり寝込んでしまった。光源氏は、柏木の神経を痛めつけた。
5 苦悩を秘めて
女三の宮は、柏木の子を生んだ。光源氏は、人前では見事につくろっているが、赤子を抱く気にはとてもなれない。女三の宮は、光源氏の内々の冷たさがますますひどくなるのを感じて尼になってしまった。柏木は、病の床で女三の宮出家のニュースを耳にし、気を落としてあの世に旅立ってしまった。
後に残された子を抱き上げる光源氏。その心の苦痛はいかばかりか。何心なく笑む幼児の顔に、柏木の面影が色濃く宿る。その子を自分の子として慈しみ育てなければならない。
三者三様の苦しみの中で、最も苛酷な荊の道を歩まされているのは、誰か? 光源氏である。『源氏物語』の作者は、最も能力のある光源氏に、最も苦しい重荷を背負わせた。 世の中で人に語れぬ苦しみくらいつらいものはない。それは、時には、人を狂気の淵に誘う力さえもっている。光源氏は、耐えた。内面は、苦しみのたうち回りながらも、表面は取り繕いつつ平静を装って、最後まで秘密を人に語ることはなかった。その精神力の強さに私は大人の魅力を感じる。
人間の持つ業に苦しみ、時には、耐えきれずにそれをふと表面化させてしまっては、反省する光源氏。そこには、もはや、若かりし頃の理想的な造りものめいた光源氏は存在しない。悩み、のたうち回って苦しみに耐えようとする、リアリティあふれる熟年男性がいる。中年以後の人間の匂い溢れる光源氏の姿は、『源氏物語』が古代の物語という枠を超えて、人間をえぐり出す小説として現代まで生きながらえてきた要因の一つだ、と私は思う。
生きるとはどういうことなのか? 中年以後の光源氏は、われわれに最も根源的な問いを投げかけ続ける魅力的な存在である。
(以上は『AERA MOOK(アエラ・ムック)』特集27号に掲載したものです。なお、上記文章は、山口仲美『源氏物語を楽しむ─恋のかけひき─』660円 丸善株式会社 にはいっています。興味のおありの方は、お読みください。)
|
|
|
|
 |
 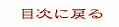 |
 |
|