 |
<学会(研究会)口頭発表> |
 |
|
(1)昭和44年 6月 単独 「比喩の表現論的性格と文体論への応用」
(日本文体論協会大会)
|
|
|
宇津保物語と源氏物語を具体例にして、比喩表現の分析が、いかに文体の特色をさぐるのに有効であるかをのべたもの。 |
|
|
(2)昭和44年10月 単独 「今昔物語集の文体に関する一考察―『事無限シ』をめぐって―」
(国語学会秋季大会)
|
|
|
今昔物語集に頻出する「事无限シ」の表現に注目して、同作品の文体の性格を考察したもの。 |
|
|
(3)昭和45年11月 単独 「今昔物語集の象徴詞―表現論的考察―」
(表現学会全国大会) |
|
|
今昔物語集は象徴詞に富むと考えられてきたが、実態調査からその従来説を覆したもの。 |
|
|
(4)昭和47年 5月 単独 「中古象徴詞の語音構造」
(国語学会春季大会)
|
|
|
濁音表記が不完全であるために、その読みが不明である中古象徴詞を語誌と語音構造から解明したもの。 |
|
|
(5)昭和48年10月 単独 「平安朝文章史研究の一視点―文連接法を中心に―」
(国語学会秋季大会) |
|
|
文連接法から、平安時代の文章をとらえると、和文性・訓読性の他に、口誦性という観点も導入してとらえる必要のあることを述べたもの。 |
|
|
(6)昭和52年 5月 単独 「歴史的現在法の文体論的意味―平安日記文学を中心として―」
(表現学会全国大会)
|
|
|
歴史的現在法の分析が、どれほど文体研究に有効であるかを平安日記文学を例にして考察したもの。 |
|
|
(7)昭和55年10月 単独 「源氏物語の表現―並列された形容語の分析から―」
(国語学会秋季大会)
|
|
|
源氏物語に頻出する並列形容語を分析することによって、源氏物語の表現方法を追究したもの。 |
|
|
(8)昭和56年10月 単独 「源氏物語の象徴詞」
(物語研究会)
|
|
|
源氏物語の象徴詞の性格を、今昔物語集のそれとの比較を通して、明らかにしたもの。 |
|
|
(9)昭和58年 4月 単独 「源氏物語の象徴詞―その独自の用法―」
(国語語彙史研究会)
|
|
|
源氏物語の象徴詞が人物によって使い分けられている実態を明らかにし、源氏物語の表現方法の解明を意図したもの。 |
|
|
(10)昭和61年 7月 単独 「音象徴語に関する一考察―虫の音の系譜―」
(表現学会例会)
|
|
|
枕草子にみられる「ちちよちちよ」という蓑虫の声の意味、古今和歌集にみられる「つづりさせてふきりぎりすなく」の意味の解明を行ないながら、虫の音をうつす擬音語の性格を解き明かしたもの。 |
|
|
(11)昭和62年 7月 単独 「源氏物語の表現方法」
(紫式部学会)
|
|
|
源氏物語の文体の魅力を、比喩表現・朧化表現・擬声語・擬態語・並列形容語などの面から追究したもの。 |
|
|
(12)昭和62年11月 単独 「実証主義の可能性―和泉式部日記の文体をめぐって―」
(東京大学国語国文学会) |
|
|
和泉式部日記の文体を例にして、実証主義的な立場に立つと、いかなる事柄が追究可能になるのかを明らかにしたもの。 |
|
|
(13)平成 6年 6月 単独 「谷崎潤一郎『細雪』の表現―『源氏物語』の影響―」
(表現学会全国大会) |
|
|
心理を写し出す表現(心話文)に注目して、『源氏物語』が、谷崎潤一郎の『細雪』に与えた影響を具体的に指摘したもの。 |
|
|
(14)平成 7年10月 単独 「モモンガの声―擬声語の史的推移―」
(日本語研究会) |
|
|
モモンガの鳴き声を写す擬声語の史的推移を明らかにしたもの。 |
|
|
(15)平成 8年11月 単独 「大型国語辞典の比較検討―意味記述をめぐって―」
(語彙・辞書研究会) |
|
|
現在刊行されている大型国語辞典の意味記述の仕方を比較検討し、望ましい意味記述のあり方を模索したもの。 |
|
|
(16)平成11年 4月 単独 「源氏物語の表現方法」
(北京日本学研究センター文学コース研究会) |
|
|
源氏物語の巧みな表現方法を具体例を挙げながら指摘したもの。 |
|
|
(17)平成11年11月 単独 「北京における日本語教育に関する現状報告と提言」
(国語審議会第三委員会) |
|
|
北京をはじめとする中国の日本語教育の現状を明らかにし、今後の日本語教育の在り方を論じたもの。 |
|
|
(18)平成12年5月 単独 「味と味覚を表す語彙と表現」
(日本語研究会) |
|
|
味を表す語彙の不足を補う表現形態について論じたもの。 |
|
|
(19)平成13年11月 単独 「擬音語・擬態語辞典の現状と課題」
(語彙・辞書研究会) |
|
|
現在刊行されている擬音語・擬態語辞典の現状を報告し、これからの課題を論じたもの。 |
|
|
(20)平成14年 1月 単独 「中国の影響を受けなかった日本説話─その巧みなレトリック─」
(埼玉大学21世紀総合研究機構 短期プロジェクト研究会) |
|
|
平安末期に成立した『今昔物語集』の中で、漢籍の影響を受けなかった説話に焦点を当て、日本独自の描写方法を明らかにしたもの。 |
|
|
(21)平成14年 3月 単独 「日本と東アジアの文化的位相に関する総合的研究」
(埼玉大学21世紀総合研究機構 研究発表会) |
|
|
日本と東アジアとの間に横たわる文化的・社会的位相の差異の解明を目指して行われている研究プロジェクトの内容説明。 |
|
|
(22)平成15年 6月 単独 「歌ことばの源流と展開」
(平成十五年度全国大学国語国文学会夏季大会シンポジウム) |
|
|
パネルディスカッションパネリストの一人。山口仲美は、「歌ことばの展開」と題して発表。 |
|
|
(23)平成15年11月 単独 「擬音語・擬態語に魅せられる」
(平成15年度国語学会秋季大会講演) |
|
|
擬音語・擬態語に対する歴史的追究が何を明らかにするのかについて解明したもの。 |
|
|
(24)平成16年11月 単独「文字世界の擬音語・擬態語とコミック世界の擬音語・擬態語」
(国学院大学国語研究会) |
|
|
|
|
|
(25)平成18年 5月 単独「係り結びの消滅」
(日本語研究会) |
|
|
|
|
 |
 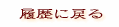 |
 |