 |
<解説・随筆・新聞コラム・教科書掲載文> |
 |
|
(1)昭和61年 8月 単著 「『今昔物語集』解説」
『もろさわようこの今昔物語集』(集英社)
|
|
|
『今昔物語集』を現代の人に親しんでもらうために、原典を分かりやすい物語に変え、さらに原典の解説を施したもの。「解説」は、次の見出し項目に従って行なった。
(1)はじめに、(2)原典の文体と欠字の謎、(3)鮮烈な原典の世界。 |
|
|
(2)昭和62年 4月 単著 「『ちんちんかもかも』考」
『文芸春秋』65巻4号
|
|
|
「ちんちんかもかも」という言葉の語源探索を、エッセイ風にまとめたもの。 |
|
|
(3)昭和62年 5月 単著 「おばあちゃんの言葉」
『かんぽ資金』108号 |
|
|
年寄りの言葉と若者の言葉の行き違いの様子、その原因をエッセイ風にまとめたもの。 |
|
|
(4)昭和63年 1月 単著 「ことばのエピソード」
『本』(講談社)13巻1号
|
|
|
日常おこる言葉の聞き違いの例をあげ、どういう時にそれが起こるのかをエッセイ風にまとめたもの。 |
|
|
(5)昭和63年 3月 単著 「気になる話しことば」
『ミセス』(文化出版局) |
|
|
現代の話しことばのうち、気になる言い方の例をあげ、なぜそういう言い方が耳ざわりなのかをエッセイ風に解きあかしたもの。 |
|
|
(6)昭和63年 5月 単著 「現代あだ名考―ネーミングの諸相・教師編―」
『産経新聞』文化欄
|
|
|
アンケートをもとに、教師についた「あだ名」をネーミングの観点からエッセイ風にまとめたもの。 |
|
|
(7)昭和63年 5月 単著 「ことばの世界への旅」
『しおり』(紀伊国屋書店)5巻21号
|
|
|
ことばに関するエピソードを、エッセイ風にまとめたもの。 |
|
|
(8)平成 1年 9月 単著 「鳥の鳴き声を聴く―ユーモラスな江戸時代の庶民感覚」
『聖教新聞』文化欄
|
|
|
江戸時代の人々が、鳥の声をどのように聞き、どんな言葉で写していたかを、エッセイ風にのべたもの。 |
|
|
(9)平成 1年11月 単著 「ある日の大学の授業」
『ハイスクール・ニューズ』 (学校図書株式会社)
|
|
|
「いろは歌」の作者に関するイメージを、エッセイ風に述べたもの。 |
|
|
(10)平成 2年 3月 単著 「犬の声」
『東京新聞』文化欄 |
|
|
昔の日本人は、犬の声をどういう言葉で写したのかといったことを、エッセイ風にまとめたもの。 |
|
|
(11)平成 2年 7月 単著 「お酒の名前」
『醸界春秋』18巻38号 |
|
|
日本酒の名前を、ネーミングの観点からエッセイ風に述べたもの。 |
|
|
(12)平成 2年11月 単著 「ドイツで語る源氏物語秘話」
『丘』(学習研究社)3号 |
|
|
ドイツにあるメリーランド大学の分校で講演した源氏物語の話と学生たちの反応をエッセイとしてまとめたもの。 |
|
|
(13)平成 3年 8月 単著 「山口仲美の新文章教室」
『月刊 日本語』3巻11号 |
|
|
「熱烈な愛の言葉をささやかれたら」「激しい拒絶の言葉をなげつけられたら」という題で、エッセイを募集し、応募作品の批評をしたもの。 |
|
|
(14)平成 3年 9月 単著 「私の出合ったステキな先生」
『灯台』372号 |
|
|
やる気を起こさせた高校時代の国語教師の思い出を綴ったもの。 |
|
|
(15)平成 3年10月 単著 「楽しい仲間」
『婦人公論』76巻10号 |
|
|
よく一緒にいる文筆業の仲間たちのことをつづったもの。 |
|
|
(16)平成 3年10月 単著 「私と英語」
『English Avenue』70号 |
|
|
四十歳を過ぎて始めた英会話の話を綴ったもの。 |
|
|
(17)平成 3年12月 単著 「源氏物語から学ぶいい夫婦関係の保ち方」
『ラ・セーヌ』6巻12号 |
|
|
よい夫婦関係を保つ秘訣を、源氏物語の夫婦関係を例にしてのべたもの。 |
|
|
(18)平成 4年 3月 単著 「日本最古のキスの記述は」
『MORE』16巻3号 |
|
|
「口を吸ふ」から初めて、キスを表す言葉の歴史を述べたもの。 |
|
|
(19)平成 4年 6月 単著 「ツクツクボウシ」
『どうぶつと動物園』44巻6号 |
|
|
現代のツクツクボウシの声の聞き方からは想像できない昔の擬声語の例を紹介したもの。 |
|
|
(20)平成 4年 6月 単著 「男と女の会話を楽しむ」
『婦人画報』1067号 |
|
|
源氏物語を例にして、魅力ある会話をするとはどういうことかを述べたもの。
同エッセイは、『王朝の香り』(京都書店・平成9年6月)にも収録された。 |
|
|
(21)平成 4年 6月 単著 「花譜―山吹の花―」
『美しいキモノ』160号 |
|
|
山吹の花にたとえられた源氏物語の女性、玉鬘のかしこさを述べたもの。 |
|
|
(22)平成 4年10月 単著 「花譜―荻の花―」
『美しいキモノ』161号 |
|
|
荻の花にたとえられた源氏物語の女性、軒端の荻のなびきやすさを述べたもの。 |
|
|
(23)平成 4年12月 単著 「花譜―山茶花―」
『美しいキモノ』162号 |
|
|
山茶花の花にまつわる思い出を綴ったもの。 |
|
|
(24)平成 4年 7月 単著 連載「平安朝'元気印'列伝」
『産経新聞』文化欄 (平成4年11月まで) |
|
|
『今昔物語集』から、現代にも通じるたくましく生きる女の話を紹介し、鑑賞していったもの。 |
|
|
(25)平成 5年 2月 単著 連載「土曜エッセー―動物の声―」
『東京新聞』夕刊 (平成5年2月末まで) |
|
|
猿・鹿・蛙・鳩の声を写す言葉について、エッセイ風にまとめていったもの。 |
|
|
(26)平成 5年 3月 単著 「今昔物語の女たち」
『聖教新聞』 |
|
|
『今昔物語集』から、心温まる夫婦愛の話を紹介し、鑑賞したもの。 |
|
|
(27)平成 5年 4月 単著 「Opinion―『源氏』のエレガントな女人よりアクティブな『今昔』女に憧れたい」
『CRER』 |
|
|
『今昔物語集』の頼もしい女性たちの魅力を述べたもの。 |
|
|
(28)平成 5年 4月 単著 連載「山口仲美の言葉の探検」
『産経新聞』文化欄 (平成5年9月まで) |
|
|
「一二三」をはじめ、日常気になる言葉を取り上げ、エッセイ風にまとめて連載していったもの。 |
|
|
(29)平成 6年 4月 単著 「犬の声」
『新編国語Ⅰ』(東京書籍) |
|
|
現在では、「ワンワン」に決まっている犬の声を写す言葉が、江戸時代までは違っていたことをエッセイ風に述べたもの。 |
|
|
(30)平成 6年 4月 単著 「お食事は致しましたか―敬語の誤り―」
『新国語Ⅱ』(大修館書店) |
|
|
敬語の使い方を分かりやすく具体例をあげながら説明したもの。 |
|
|
(31)平成 6年 5月 単著 連載「古典往来」
『産経新聞』朝刊 (平成6年10月まで) |
|
|
『竹取物語』『大和物語』『伊勢物語』をはじめとする平安文学作品に見られる、印象的な言葉や表現を指摘し、鑑賞していったもの。 |
|
|
(32)平成 6年 7月 単著 「強運の人」
『大法輪』8月号 |
|
|
ふりかかる災難を自力で払いのける勇気ある男の子の話を、『今昔物語集』から取り上げ、紹介したもの。 |
|
|
(33)平成 6年10月 単著 「リーダーの資格」
『運河』12巻10号 |
|
|
『今昔物語集』から、知恵と勇気のある武将の話を取り上げ、鑑賞したもの。 |
|
|
(34)平成 6年12月 単著 「言葉のアクシデント」
『丘』(学習研究社)12号 |
|
|
言葉のちょっとした聞き違えや読み違えの例で、ほのかな笑いを誘うようなものを取り上げ、そこに潜む心理状態を指摘したもの。 |
|
|
(35)平成 8年 5月 単著 「古典に親しむ(1)―女の悪口―『徒然草』」
『国語教育相談室』11号 (光村図書出版株式会社) |
|
|
『徒然草』の女の悪口の底流には、作者兼好の、女への並々ならぬ関心の潜んでいることを指摘したエッセイ。 |
|
|
(36)平成 8年 6月 単著 「古典に親しむ(2)―再婚の夜―『伊勢物語』」
『国語相談教室』12号 (光村図書出版株式会社) |
|
|
文学とは何か、歌とは何かを、『伊勢物語』は、激しい悲恋の話を通して我々に語りかけていることを指摘したエッセイ。 |
|
|
(37)平成 8年 9月 単著 「古典に親しむ(3)―含み笑い―『源氏物語』」
『国語相談教室』13号 |
|
|
『源氏物語』の末摘花の含み笑いの声「むむ」をはじめとして、原文のまま味わいたくなる言葉についてのべたもの。 |
|
|
(38)平成 8年11月 単著 「いつの時代も『憎きもの』」
『文化庁月報』338号 |
|
|
『枕草子』の「にくきもの」の章段には、現代のエチケット集として通用するものが含まれていることを指摘したもの。 |
|
|
(39)平成 9年 1月 単著 「古典に親しむ(4)―男心はわからない―『枕草子』」
『国語教育相談室』14号
|
|
|
『枕草子』の主張の魅力と限界を指摘したエッセイ。 |
|
|
(40)平成 9年 2月 単著 「生きていることば―若人・響け若人の歌―」
『わこうど』235号 (法務省矯正局) |
|
|
「若人」という言葉の意味の移り変わりをエッセイ風に述べたもの。 |
|
|
(41)平成 9年 2月 単著 「生きていることば―人・「幸」住むと人のいう―」
『人』2370号 (法務省矯正局) |
|
|
「人」という言葉を、自分を指すのに用いることのおかしさを指摘したもの。 |
|
|
(42)平成 9年 3月 単著 「美女になった狐」
『朱』40号 |
|
|
『今昔物語集』から、狐が人間の男に恋をして悲劇的な最期を遂げた話を紹介し、鑑賞したもの。 |
|
|
(43)平成 9年 3月 単著 「古典に親しむ(5)―語り手の登場―『堤中納言物語』」
『国語教育相談室』15号 |
|
|
物語の語り手が、顔を覗かせる瞬間のおもしろさを『堤中納言物語』を例にしてのべたもの。 |
|
|
(44)平成 9年 3月 単著 「心のふるさと」
『実践だより』68号 |
|
|
女子大のよさをエッセイ風に述べたもの。 |
|
|
(45)平成 9年 4月 単著 「卒塔婆の話」
『史窓余話』 (国史大辞典第十五巻下付録) |
|
|
『国史大辞典』では、「卒塔婆」の意味のうち、現在多用される意味の解説が欠落していることを指摘したもの。(吉川弘文館編集部編『歴史の花かご』下巻、吉川弘文館、平成10年10月にも再録された。) |
|
|
(46)平成 9年 4月 単著 「源氏物語のテクニック―破局の訪れ―」
『源氏研究』2号 (翰林書房) |
|
|
『源氏物語』は、光源氏と朧月夜との密会が暴露され破局に至るまでのプロセスを、極めて優れたテクニックを駆使して描いていることを指摘したもの。 |
|
|
(47)平成 9年 4月 単著 「生きていることば―敬語の使い道―」
『人』2372号 (法務省矯正局)
『わこうど』237号(法務省矯正局) |
|
|
敬語を使うのは、心理的にどういう場合なのかを具体的に指摘したもの。 |
|
|
(48)平成 9年 6月 単著 「おどろおどろしい言葉二つ―「餓死」と「堕胎」―」
『食品と容器』38巻6号 (缶詰技術研究会) |
|
|
「餓死」と「堕胎」という忌まわしい言葉が、何時からどのような使われ方をしてきたのかを明らかにしたもの。 |
|
|
(49)平成 9年 6月 単著 「生きていることば―「チュー」して―」
『人』2374号 (法務省矯正局)
『わこうど』239号(法務省矯正局) |
|
|
キスにまつわる言葉の歴史を述べたもの。 |
|
|
(50)平成 9年 6月 単著 「男と女の会話を楽しむ」
『王朝の香り』(京都書院) |
|
|
『源氏物語』を男と女の会話から読むと、実に興味深いことを指摘したもの。 |
|
|
(51)平成 9年 7月 単著 「光源氏に見る男の魅力」
『AERA MOOK(アエラムック)』 特集27「『源氏物語』が分かる」 |
|
|
光源氏が、人間としての魅力を発揮しだしたのは、苦悩を一身に背負いじっと耐える姿勢を見せる中年からであることを指摘したもの。 |
|
|
(52)平成 9年 7月 単著 連載「窓辺」
『静岡新聞』(夕刊)第一面 |
|
|
「昔の言葉はエレガント?」「マロのつく名前はいかが」「読めない名前」「本当ならいいなの薬名」「『会う』に顔を赤らめる」「『はぁ』って感じ」「食べ終わったのに『おあがり』」「歌に『殺す』」「人の名前のつけ方」「なつかしき『クヮ』『グヮ』の音」「兎は『一羽』」「虫は『針させ綴りさせ』」「きらっと光るお酒の名前」と、言葉に関するエッセイを連載していったもの。
(平成9年9月まで) |
|
|
(53)平成 9年 8月 単著 「古典に親しむ(6)―どのみち死ぬならやってみる―『今昔物語集』」
『国語教育相談室』17号
|
|
|
『今昔物語集』の話を例にして、古典を読んでいて勇気づけられることを、述べたもの。 |
|
|
(54)平成 9年 8月 単著 「生きていることば―「夫婦」は、なぜ「めおと」―」
『人』2376号 (法務省矯正局)
『わこうど』241号(法務省矯正局) |
|
|
「夫婦」と書いて、なぜ「めおと」と読むのかを述べたエッセイ。 |
|
|
(55)平成 9年 9月 単著 「古典に親しむ―(7)女の気持―『蜻蛉日記』」
『国語教育相談室』18号 |
|
|
一夫多妻制下に自分がいると仮想してみると、『蜻蛉日記』の作者の気持ちが良く理解できることを述べたエッセイ。 |
|
|
(56)平成 9年10月 単著 「生きていることば―昔の言葉はエレガント?―」
『人』2378号 (法務省矯正局)
『わこうど』243号(法務省矯正局) |
|
|
王朝文学に見られる「青ヘド」「糞マル」などの言葉を紹介し、雅やかな文学という思いこみを指摘したもの。 |
|
|
(57)平成 9年11月 単著 「古典に親しむⅡ―(8)立石寺―『奥の細道』」
『国語教育相談室』19号 |
|
|
実際に現地に赴いてみると、芭蕉の俳文の巧みさが具体的に見えてくることを指摘したもの。 |
|
|
(58)平成 9年12月 単著 「生きていることば―「達者」と「達人」―」
『人』2380号 (法務省矯正局)
『わこうど』245号(法務省矯正局) |
|
|
「達者」と「達人」という類義語を、勢力争いの構図からその史的推移を捉えたもの。 |
|
|
(59)平成10年 2月 単著 「古典に親しむⅡ―(9)消えた音―『宇治拾遺物語』」
『国語教育相談室』20号 |
|
|
「ごぶごぶ」という水の音を写す言葉が、昔は存在し、「五部五部」に掛けて笑い話になったりして活躍していたことを述べたもの。 |
|
|
(60)平成10年 4月 単著 「古典に親しむⅡ―(10)鶯の鳴きつる花―『古今和歌集』」
『国語教育相談室』21号 |
|
|
「待つ人も来ぬものゆゑに鶯の鳴きつる花を折りてけるかな」という歌の、新しい解釈を提示したもの。 |
|
|
(61)平成10年 4月 単著 「私の高校時代」
『篁会報』9号 |
|
|
教え方の上手な高校の国語教師との出会いを綴ったもの。 |
|
|
(62)平成10年 7月 単著 「言葉の探検をしてみませんか」
『刑政』109巻7号 |
|
|
言葉に興味を抱くと見えてくる世界について、具体的に述べたもの。 |
|
|
(63)平成11年 6月 単著 「メイクワンシーの国」
『センター通信』66号 |
|
|
中国人の大雑把さをエッセイ風にまとめたもの。 |
|
|
(64)平成12年 1月 単著 「本はともだち」
『国語教育相談室』27号 |
|
|
中学生に親しんでもらいたい古典文学作品を例示し、その魅力を述べたもの。 |
|
|
(65)平成12年 9月 単著 「活気に満ちた中国人学生」
『青淵』618号 |
|
|
北京師範大学の学生たちに日本語の話を講演したときの彼らの活気に満ちた反応を述べたもの。 |
|
|
(66)平成12年10月 単著 「表紙絵の言葉 ピエロの昼休み」
『青淵』619号 |
|
|
表紙になった自分の絵についての解説。 |
|
|
(67)平成12年11月 単著 「象のすすり泣き」
『野鳥』65巻10号 |
|
|
数頭の大象が、小さな象舎に飼われている北京動物園での、胸締め付けられる思いをつづったもの。 |
|
|
(68)平成13年 3月 単著 「吉田先生のホントの気持ち」
『埼玉大学吉田康彦教授退官記念文集』 |
|
|
国際協力研究は、これからの国際社会では必要であることを述べたもの。 |
|
|
(69)平成13年 3月 単著 「融通無碍」
『星座』(かまくら春秋社)1巻2号 |
|
|
北京で、数字をめぐる融通無碍な解釈に遭遇して見事にやられた体験エピソード。 |
|
|
(70)平成13年 3月 単著 「鶯の声二題」
『邦楽、西洋と比ぶれば─九』 紀尾井邦楽スペシャル |
|
|
江戸時代の鶯にまつわる笑い話を二つ紹介したもの。 |
|
|
(71)平成13年11月 単著 「中学古典への親しみ方(一)」
『Mitsumura Mail Magazine』 |
|
|
生徒を古典好きにするための、教師用手引書 |
|
|
(72)平成13年11月 単著 「中学古典への親しみ方(二)」
『Mitsumura Mail Magazine』 |
|
|
古典興味を持たせるための補助教材の選び方指南 |
|
|
(73)平成13年12月 単著 「中学古典への親しみ方(三)」
『Mitsumura Mail Magazine』 |
|
|
古典好きになった自己体験を述べたもの |
|
|
(74)平成14年4月 単著 「『おざなり』と『なおざり』」
『文化庁月報』403号 |
|
|
「おざなり」と「なおざり」の意味の違いを述べたもの |
|
|
(75)平成14年5月 単著 「『ブ』の音の不思議」
『文化庁月報』404号 |
|
|
「がぶがぶ」「ざぶざぶ」「しゃぶしゃぶ」と「ブ」音には、ある意味が込められていることを述べたもの |
|
|
(76)平成14年6月 単著 「気になる言葉」
『文化庁月報』405号 |
|
|
若者たちが、自ら気になると述べている言葉をあげ、めーるとの関係を考えたもの。 |
|
|
(77)平成14年7月 単著 「電子文明の音がする」
『文化庁月報』406号 |
|
|
三〇年前には決して見られなかった擬音語群。そこに現代文明が浮き彫りにされていることを述べたもの。 |
|
|
(78)平成14年8月 単著 「ニャンの声には艶があった」
『文化庁月報』407号 |
|
|
江戸時代の猫の声「にゃん」は独特な意味を帯びていたことを述べたもの。 |
|
|
(79)平成14年9月 単著 「掛詞で聞いた蝉の声」
『文化庁月報』408号 |
|
|
蝉の声におのれの心情を託して面白おかしく聞きなしていた昔を紹介し、現代の都会生活を反省したもの。 |
|
|
(80)平成14年10月 単著 「言葉の力」
『文化庁月報』409号 |
|
|
弱っている人間の心を勇気付ける言葉の数々を実際の調査や体験に基づいて述べたもの |
|
|
(81)平成14年10月 単著 「クイズ擬音語の話」
『聖教新聞』文化欄 |
|
|
|
|
|
(81)平成14年11月 単著 「クイズ擬音語の話」
『文化庁月報』410号 |
|
|
「ねうねう」という昔の猫の声に、日本人はどんな意味を聞いたのか?などをはじめ、擬音語にまつわる面白い話をしたもの。 |
|
|
(82)平成14年11月 単著 「巻頭言 謎解きの魅力」
『日本語学』21巻11号 |
|
|
|
|
|
(83)平成14年11月 単著 「鶯の「ホーホケキョー」の声は「法法華経」の意味ってほんと?」
『日本語学』21巻11号 |
|
|
|
|
|
(84)平成14年12月 単著 「クイズ擬音語・擬態語」
『青淵』645号 |
|
|
「ぐりりににぐりりにに」は何の声?などをはじめ、クイズ形式で擬音語・擬態語にまつわる話を分かりやすく述べたもの。 |
|
|
(85)平成14年12月 単著 「犬は「びよ」と鳴いていた─日本語は擬音語・擬態語が面白い─」
『欅』(埼玉大学広報誌) |
|
|
|
|
|
(86)平成14年12月 単著 「『夫婦』のぬくもり」
『文化庁月報』403号 |
|
|
[夫婦」をなぜ「めおと」と読むのか?また、そう読むとき「ふうふ」と読むときとは違い、ほのかなぬくもりの漂うことを指摘したもの。 |
|
|
(87)平成15年 1月 単著 「『とつぐ』って何?」
『文化庁月報』通巻412号 |
|
|
|
|
|
(88)平成15年 2月 単著 「擬音語大好き」
『かんぽ資金』通巻297号 |
|
|
|
|
|
(89)平成15年 2月 単著 「表紙絵のことば」
『青淵』647号 |
|
|
|
|
|
(90)平成15年 2月 単著 「授業点描」
『読売新聞 埼玉版』2月2日 |
|
|
|
|
|
(91)平成15年 2月 単著 「二月の随想─天狗が鳴いた」
共同通信社配信のコラム
(新潟日報・徳島新聞・静岡新聞・山陽新聞・熊本日日新聞・神戸新聞・愛媛新聞・信濃毎日新聞・埼玉新聞・長崎新聞・東都新聞などに掲載された) |
|
|
|
|
|
(92)平成15年 2月 単著 「ヒャラリヒャラリコ」
『文化庁月報』413号 |
|
|
|
|
|
(93)平成15年 2月 単著 「狐の機嫌の悪い時の声を教えて」
『週刊新潮』掲示板48巻7号 |
|
|
|
|
|
(94)平成15年 3月 単著 「チントンシャン─楽器の音色─」
『潮』529号 |
|
|
|
|
|
(95)平成15年 3月 単著 「擬音語好きの一茶さん」
『星座』14号 |
|
|
|
|
|
(96)平成15年 3月 単著 「もとは擬音語!」
『文化庁月報』414号 |
|
|
|
|
|
(97)平成15年 3月 単著 「うぐいす大学」
『読売新聞 埼玉版』3月9日 |
|
|
|
|
|
(98)平成15年 3月 単著 「擬音語好きの一茶さん」
『星座』1巻14号 |
|
|
|
|
|
(99)平成15年 4月 単著 「そよそよ」
『しんぶん赤旗』4月13日 |
|
|
|
|
|
(100)平成15年 4月 単著 「通訳の授業」
『読売新聞 埼玉版』4月13日 |
|
|
|
|
|
(101)平成15年 4月 単著 「詩の言葉」
『文化庁月報』415号 |
|
|
|
|
|
(102)平成15年 5月 単著 「作詩の秘密―オノマトペからさぐる―」
『星座』15号 |
|
|
|
|
|
(103)平成15年 5月 単著 「デレスケボーコー」
『読売新聞 埼玉版』5月18日 |
|
|
|
|
|
(104)平成15年 5月 単著 「へぐへぐ」
『しんぶん赤旗』5月18日 |
|
|
|
|
|
(105)平成15年 5月 単著 「北京の大学で『山椒魚』を読む」
『文化庁月報』416号 |
|
|
|
|
|
(106)平成15年 6月 単著 「北京で握手」
『読売新聞 埼玉版』6月22日 |
|
|
|
|
|
(107)平成15年 6月 単著 「中国ではゲルゲルゲル」
『文化庁月報』417号 |
|
|
|
|
|
(108)平成15年 6月 単著 「天狗が困る」
『しんぶん赤旗』6月22日 |
|
|
|
|
|
(109)平成15年 7月 単著 「幸田文さんの文章」
『星座』16号 |
|
|
|
|
|
(110)平成15年 7月 単著 「つぶつぶ」
『しんぶん赤旗』7月27日 |
|
|
|
|
|
(111)平成15年 7月 単著 「平安時代の流行語」
『文化庁月報』418号 |
|
|
|
|
|
(112)平成15年 9月 単著 「短歌と擬音語」
『星座』17号 |
|
|
|
|
|
(113)平成15年11月 単著 「スッペラポーと鳴く鶯」
『星座』18号 |
|
|
|
|
|
(114)平成16年 1月 単著 「猿はココと鳴いていた」
『しんぶん赤旗』12月28日・1月4日合併号 |
|
|
|
|
|
(115)平成16年 1月 単著 「『擬音・擬態語辞典』の舞台裏」」
『星座』19号 |
|
|
|
|
|
(116)平成16年 2月 単著 「音の生まれる場所107回 擬音語にこだわる」
『教育音楽』音楽之友社 48巻2号 |
|
|
|
|
|
(117)平成16年 3月 単著 「タブーの範囲」
『新潮』3 101巻3号 |
|
|
|
|
|
(118)平成16年 3月 単著 「中国の日本語教師たち」
『星座』20号 |
|
|
|
|
|
(119) 平成17年 3月 単著 「豊穣な言語」 |
|
|
『文芸春秋』特別版3月臨時増刊号 |
|
|
(120) 平成17年 7月 単著 「幸運な出会い」 |
|
|
『出版情報』講談社 |
|
|
(121) 平成17年10月 単著 「こころにひかる物語―魑魅魍魎からの解放―」 |
|
|
『かまくら春秋』426号 |
|
|
(122) 平成18年 4月 単著 「歌の意味を教えてください」『小学国語通信 ことばだより』
平成18年春号教育出版 |
|
|
|
|
|
(123) 平成18年10月 3日 にほんごチェック 「フツーにうまい」元気な若者ことば
日本経済新聞夕刊 |
|
|
|
|
|
(124) 平成18年10月10日 にほんごチェック 気になる言葉は「巨…」滑稽感にじみ出る
日本経済新聞夕刊 |
|
|
|
|
|
(125) 平成18年10月17日 にほんごチェック 「すごい面白い」認めたい強調表現
日本経済新聞夕刊 |
|
|
|
|
|
(126) 平成18年10月24日 にほんごチェック 「ごぼう抜き」懐かしい言葉に心和む
日本経済新聞夕刊 |
|
|
|
|
|
(127) 平成18年10月31日 にほんごチェック 「みんなゴールキーパーだった」会話術の極意
日本経済新聞夕刊 |
|
|
|
|
|
(128) 平成18年11月 7日 にほんごチェック 時代劇の「おめー」現代語と上手にミックス
日本経済新聞夕刊 |
|
|
|
|
|
(129) 平成18年11月14日 にほんごチェック 「やむをえない」語源が忘れられていく
日本経済新聞夕刊 |
|
|
|
|
|
(130) 平成18年11月21日 にほんごチェック 「幼なじみ」幼年時代のほのかな恋の記憶
日本経済新聞夕刊 |
|
|
|
|
|
(131) 平成18年11月28日 にほんごチェック 「カワユス」ふふふ、成り立ち解けた
日本経済新聞夕刊 |
|
|
|
|
|
(132) 平成18年12月 5日 にほんごチェック 「矛盾してますね」鋭い推理力を示す言葉
日本経済新聞夕刊 |
|
|
|
|
|
(133) 平成18年12月12日 にほんごチェック フインキ「雰囲気」の発音に異変
日本経済新聞夕刊 |
|
|
|
|
|
(134) 平成18年12月19日 にほんごチェック 「気分はマンドリン」昔のおしゃれな流行語
日本経済新聞夕刊 |
|
|
|
|
|
(135) 平成18年12月26日 にほんごチェック 「ガイシャ」きらりと光る業界用語
日本経済新聞夕刊 |
|
|
|
|
|
(136) 平成18年 1月 9日 にほんごチェック 「ちはやぶる」幼児番組、豊かな趣向
日本経済新聞夕刊 |
|
|
|
|
|
(137) 平成19年 1月16日 にほんごチェック 「ピン芸人」芸能界の言葉がぽろり
日本経済新聞夕刊 |
|
|
|
|
|
(138) 平成19年 1月23日 にほんごチェック 「男前」女にも使う言葉?
日本経済新聞夕刊 |
|
|
|
|
|
(139) 平成19年 1月30日 にほんごチェック 「胸美帯」昔も今も悩みは尽きず
日本経済新聞夕刊 |
|
|
|
|
|
(140) 平成19年 2月 6日 にほんごチェック 「入り待ち」警察用語はちょっと怖い
日本経済新聞夕刊 |
|
|
|
|
|
(141) 平成19年 2月13日 にほんごチェック 「嫁ぐ」言葉の意味は移り変わる
日 本経済新聞夕刊 |
|
|
|
|
|
(142) 平成19年 2月20日 にほんごチェック 「旦那さん」敬語意識そのものが変化?
日本経済新聞夕刊 |
|
|
|
|
|
(143) 平成19年 2月27日 にほんごチェック 「なんだい?」コミック的なダジャレ生きる
日本経済新聞夕刊 |
|
|
|
|
|
(144) 平成19年 3月 6日 にほんごチェック 「天ぷら」外来語抜きの会話は困難
日本経済新聞夕刊 |
|
|
|
|
|
(145) 平成19年 3月13日 にほんごチェック 「嫉妬」人間ドラマ引っ張る情念
日本経済新聞夕刊 |
|
|
|
|
|
(146) 平成19年 3月20日 にほんごチェック 「かずのこ」古語の「かどのこ」が変化
日本経済新聞夕刊 |
|
|
|
|
|
(147) 平成19年 3月27日 にほんごチェック 「大事なものは目には見えない」心で見る大切さ示す
日本経済新聞夕刊 |
|
|
|
|
|
(148) 平成19年 4月 単著 「検索されるキーワードの共通点」
『宣伝会議』714号 |
|
|
|
|
|
(149) 平成19年 4月 3日 にほんごチェック 「ホワイトナイト」お姫様を守る役だが
日本経済新聞夕刊 |
|
|
|
|
|
(150) 平成19年 4月10日 にほんごチェック「オンミツ」忘れられてゆく読み
日本経済新聞夕刊 |
|
|
|
|
|
(151) 平成19年 4月17日 にほんごチェック 「デッパツ」仲間意識強める “若者言葉”
日本経済新聞夕刊 |
|
|
|
|
|
(152) 平成19年 4月24日 にほんごチェック 「たーしたーし」本当は「左へ」の方言だが…
日本経済新聞夕刊 |
|
|
|
|
|
(153) 平成19年 4月 単著 「私の三冊」
『岩波文庫私の三冊』岩波書店 |
|
|
|
|
|
(154) 平成19年 5月 1日 にほんごチェック「冤罪」漢字は意味で覚える
日本経済新聞夕刊 |
|
|
|
|
|
(155) 平成19年 5月 7日 にほんごチェック ブッポウソウ 鳴き声はブッパン?
日本経済新聞夕刊 |
|
|
|
|
|
(156) 平成19年 5月15日 にほんごチェック 「ごっつぁんです」懐深い便利な言葉
日本経済新聞夕刊 |
|
|
|
|
|
(157) 平成19年 5月22日 にほんごチェック 「空気読めよ」ドラマで知る若者言葉
日本経済新聞夕刊 |
|
|
|
|
|
(158) 平成19年 5月29日 にほんごチェック 「流れ足」動きを削った能の所作
日本経済新聞夕刊 |
|
|
|
|
|
(159) 平成19年 6月 5日 にほんごチェック 「本杉さん」思い違いが笑いを提供
日本経済新聞夕刊 |
|
|
|
|
|
(160) 平成19年 6月12日 にほんごチェック 「顔上げて!」敗者をねぎらう優しさ
日本経済新聞夕刊 |
|
|
|
|
|
(161) 平成19年 6月19日 にほんごチェック 「良心」神に近づく階段を上る
日本経済新聞夕刊 |
|
|
|
|
|
(162) 平成19年 6月26日 にほんごチェック「あのね」日本居住の経験示す
日本経済新聞夕刊 |
|
|
|
|
|
(163) 平成19年 7月 3日 にほんごチェック「誇り」自分を支える最後の砦
日本経済新聞夕刊 |
|
|
|
|
|
(164) 平成19年 7月10日 にほんごチェック「根継ぎ」技術が残れば言葉も残る
日本経済新聞夕刊 |
|
|
|
|
|
(165) 平成19年 7月17日 にほんごチェック「ジンさん」「かよっぺ」…あだ名より愛称
日本経済新聞夕刊 |
|
|
|
|
|
(166) 平成19年 7月24日 にほんごチェック「夫婦」めおと、と読むのはなぜ?
日本経済新聞夕刊 |
|
|
|
|
|
(167) 平成19年 7月31日 にほんごチェック「加齢臭」社会の課題示す新語
日本経済新聞夕刊 |
|
|
|
|
|
(168) 平成19年 8月 7日 にほんごチェック「鉄船」 辞書に残る信長の創意
日本経済新聞夕刊 |
|
|
|
|
|
(169) 平成19年 8月14日 にほんごチェック「火の国」語源は熊本沿岸の火?
日本経済新聞夕刊 |
|
|
|
|
|
(170) 平成19年 8月21日 にほんごチェック「しゃらくさい」古めかしさ、妙な親しみ
日本経済新聞夕刊 |
|
|
|
|
|
(171) 平成19年 8月28日 にほんごチェック「うなずき」日本では会話の一部
日本経済新聞夕刊 |
|
|
|
|
|
(172) 平成19年 9月 4日 にほんごチェック「祭典」葬儀にも明るいイメージ
日本経済新聞夕刊 |
|
|
|
|
|
(173) 平成19年 9月11日 にほんごチェック「ハリのないハチ」意味がわかる喜び
日本経済新聞夕刊 |
|
|
|
|
|
(174) 平成19年 9月18日 にほんごチェック「へたも絵のうち」作品通して知る深い意味
日本経済新聞夕刊 |
|
|
|
|
|
(175) 平成19年 9月25日 にほんごチェック「くそー」若い女性のむき出しの心
日本経済新聞夕刊 |
|
|
|
|
|
(176) 平成19年 8月20日 「青い鳥は身近なところに」
『日本エッセイスト・クラブ 会報』59号―Ⅰ |
|
|
|
|
|
(177) 平成19年10月3日 「動物たちの意外な鳴き声」
『国立能楽堂』290号 |
|
|
|
|
|
(178) 平成19年10月15日 「日本語力をつける」
『明治』36号 |
|
|
|
|
|
(179) 平成19年10月23日 「こけこっこう うはうは」
『広辞苑ものがたり』 |
|
|
|
|
|
(180) 平成19年11月30日 「うまく使えば何でも分かる」
『KOTONOHA―日本語、ありのまま』独立行政法人国立国語研究所 |
|
|
|
|
|
(181) 平成20年1月1日 「青春の一作―『徒然草』―」
『星座』43号 |
|
|
|
|
|
(182) 平成20年6月10日 「若者はなぜ若者言葉をつかうのか」
『全人』718号 |
|
|
|
|
|
(183) 平成20年9月30日 「新所員紹介―山口仲美」
『明治大学人文科学研究所所報』52号 |
|
|
|
|
|
(184) 平成20年12月1日 「『滑稽稿』と鶏が啼く」
『本』講談社33巻12号 |
|
|
|
|
|
(185) 平成21年1月1日 単著「雌牛は『メー』と鳴く?」
『しんぶん赤旗』日曜版・新年号 |
|
|
|
|
|
(186) 平成21年11月1日 「『癌』という言葉」
『経済Trend』57巻11号 |
|
|
|
|
|
(187) 平成21年12月 単著「掲示板」
『週刊新潮』55巻49号 |
|
|
|
|
|
(188) 平成22年2月15日 「生きたしと思うべきなり」
『日本エッセイスト・クラブ 会報』61号―Ⅲ |
|
|
|
|
|
(189) 平成22年3月頃 単著 「言葉を的確に使おう」
『日本語検定受験案内』 |
|
|
|
|
|
(190) 平成22年7月15日 「明大からの処方箋―若者言葉に耳をすませば―」
『明治』47号 |
|
|
|
|
|
(191) 平成23年02月23日「きのうきょう 知られざる古典の魅力を言葉から解き明かす」
『聖教新聞』 |
|
|
|
|
|
(192) 平成23年4月1日「さるは『ココ』と鳴いていた」
『小学国語 ひろがる言葉 六上』(小学校国語科用教科書・平成22年3月16日検定済み)教育出版 |
|
|
|
|
|
(193) 平成23年4月 単著「古典の言葉は意外に身近で面白い」
『ごけん』東京書籍(株)検定事業部 |
|
|
|
|
|
(194) 平成23年5月18日「エッセイ私が中学生だった頃―熱血先生に出会う―」
『ことばの学び』(平成24年度版中学生の国語教科書特集号)三省堂 |
|
|
|
|
|
(195) 平成23年5月28日「底に流れる人間愛」
『シリーズ牧水賞の歌人たち 小島ゆかり』青磁社 |
|
|
|
|
|
(196) 平成23年12月23日 単著「クイズ 狐の鳴き声」
『朱』55号 |
|
|
|
|
|
(197) 平成24年1月 単著「日文版序」
『日語史』北京大学出版会 |
|
|
|
|
|
(198) 平成24年4月1日「古典の中の擬声語・擬態語」
『中学国語2 伝え合う言葉』(中学校国語科用教科書)教育出版 |
|
|
|
|
|
(199) 平成24年4月1日「日本語を見つめる」
『中学生の国語 学びを広げる 三年』(中学校国語科用教科書)三省堂 |
|
|
|
|
|
(200) 平成24年7月5日単著「男が通いたくなる家」
『月刊 不動産流通』362号 |
|
|
|
|
|
(201) 平成24年7月27日 単著「いやはや語辞典―やむおえない―」
『読売新聞』夕刊 |
|
|
|
|
|
(202) 平成24年10月1日 単著「弘法筆を選ぶ―鉛筆の思い出二つ―」
『星座』63号 |
|
|
|
|
|
(203) 平成24年10月29日 単著「展宏先生とのおつきあい」
『春 川崎展宏全句集 栞』ふらんす堂 |
|
|
|
|
|
(204) 平成24年11月15日 単著「ヒントをくれた連載」
『日本語学』31巻14号 |
|
|
|
|
|
(205) 平成25年1月24日号 単著「掲示板」
『週刊新潮』58巻3号 |
|
|
|
|
|
(206) 平成25年4年1日「なんてステキな光景なの!―春はあけぼの―」
北原保雄ほか編『新編国語総合』(高校用国語教科書)大修館書店 |
|
|
|
|
|
(207) 平成25年4月19日 単著「もったいない語辞典―したり顔―」
『読売新聞』夕刊 2面 |
|
|
|
|
|
(208) 平成26年2月26日号 単著「私の週間食卓日記」
『週刊新潮』60巻8号(2978号) |
|
|
|
|
|
(209) 平成26年7月1日 単著「『蚊』という名前はなぜ付いた?」
『青淵』784号 |
|
|
|
|
|
(210) 平成26年7月10日 単著「『大学教授がガンになってわかったこと』の後日談」
『神奈川県医師会報』776号 |
|
|
|
|
|
(211) 平成26年9月1日 単著「戦争への道」
『mybみやびブックレット』49号 |
|
|
|
|
|
(212) 平成26年11月24日 単著「交遊抄―秘めた優しさ」
日本経済新聞 文化面 |
|
|
|
|
|
(213) 平成27年4月 単著「生き方を変える」
『無添加通信』153号 |
|
|
|
|
|
(214) 平成27年6月1日 単著「擬音語・擬態語の魅力」
『本』(講談社)40巻6号 |
|
|
|
|
 |
 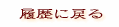 |
 |