 |
|
 |
|
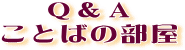
| Q. |
「キス」とか「チュー」って、昔の人もしたと思うんですが、昔は、それを何て言っていたんですか?(10/8更新) |
| A. |
最近、人前でキスをしているカップルを見かけることが多くなりました。私など、気が弱いものですから、見ては悪いような気がして、素知らぬ振りをして通り過ぎたり、視線を外したりして、結構苦労しています。
しばらく前に、テレビのCMで、「ねえ、チューして」と言って、女の子が男の人にキスをせがんでいる場面がありました。あれから、「チュー」の言葉は、すっかり有名になりました。若い人たちは、路上でするキスを「路チュー」と言うんだそうですね。私の友達は、「路チュー」と聞いて「路上駐車」のことだと思ってました。今や「キス」は、古くさく、「チュー」の方が新しく爽やかな語感を持ちはじめているのでしょうか。
「チュー」は、キスの時に出る音を写す擬音語から来た言葉です。「キス」の方は、言わずと知れた、英語「KISS」から来た外来語です。明治維新とともに、日本に広まり、使われ出しました。その時に、「KISS」の翻訳語として、「接吻(せっぷん)」「口づけ」という言葉も同時に使われています。けれども、「接吻」「口づけ」の語は「キス」「キッス」の語に押されてしだいに使われなくなっていきました。
さて、さて、「キス」という言葉がない時代には、一体、あの行為を何といったのでしょうか? まさか、日本には、あの行為はなかったとは思えませんね。西洋人のように、人前で挨拶がわりにすることこそありませんが、人間の愛し合う行為は、古今東西不変です。ディープキッスもしくはバキュームキッスに該当する言葉は、ちゃんとあります。
「口を吸う」です。平安時代の初めの『土佐日記』にこんな文があります。
ただ押鮎の口をのみぞ吸ふ。この吸ふ人々の口を押鮎もし思ふやうあらむや。
元旦のことです。船旅で、船の上には新年を祝う食べ物が何もありません。恋しい人もいません。仕方がないので、押鮎の口を吸っているというのです。押鮎って、土左ー高知県ーの名物なんですね。それをしゃぶっているのを接吻している様子に見立てたんです。鮎の方も、口を吸う人々のことをいとしいと思うことがあるかしらん、なんて、貫之さんが冗談を言っています。
『今昔物語集』にも、悪ふざけの過ぎる男が、亀を逃げたもとの妻に見立てて口を吸ったところ、亀に食いつかれてもがき苦しんだという話があります。それに懲りて、その男は、馬鹿な真似はしなくなったとサ、なんて話の最後に書いてあります。
もっと気味の悪い話もあります。同じく『今昔物語集』という平安末期の作品に収録されている話です。大江定基という人がいました。慈悲深く学問もよくできた男でしたが、ふとしたきっかけから、若く美しい女を愛するようになった。嫉妬に狂う本妻とも別れ、彼女を連れて任国の三河国ー愛知県ーに下っていった。けれども彼女は、重病にかかり、任地先であっけなく死んでしまった。定基は、悲しみに耐えられずに女を葬らずに抱いて寝ていた。数日経って女の口を吸ったところ、なんとも言えぬ臭い匂いが出てきてしまい、泣く泣く葬ったというちょっぴりぞっとする部分のある話です。でも、終わりがいいんです。定基は、やがてこの世は憂きものと悟り、出家して修行を積んで立派な僧になったとサというのです。
江戸時代まで、日本人は、こんなふうに「口を吸う」と言っていました。そのものズバリといった表現です。面白い川柳があります。
口を吸ふ 時に困ると 天狗言い
そうだろ、そうだろと妙に納得してしまう句ですね。
(以上は、私の著書『言葉の探検』小学館に掲載されている一章からです。)
|
|
|
|
 |
 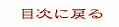 |
 |
|