 |
|
 |
|
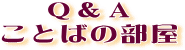
| Q. |
私は、文字の形に興味があります。何か文字を使った遊びはありませんか?(11/4更新) |
A.
|
それでは、ちょっと目に触れにくい昔の文字をめぐる謎々遊びを紹介します。
漢字の字形が簡略化されてまいりますと、楽しい文字あそびが減ってしまう気が、私なんかするんですね。むろん、私は、コチコチ頭ではないつもりですから、書く労力がへるのは大歓迎ですが、失われる楽しさもあることに気づきたい気もするわけです。
たとえば、「恋人」の「恋」という字。ちょっと古い字体を思い出して下さい。「糸」を二つ書いて、その間に「言う」という字を入れて、下に「心」を書いて出来上がる。「戀」ですね。こういう難しい字だから、「戀」という字を「糸し糸しと言う心」なんて言って覚えるわけですね。意味もよくあらわしていて、いいですね。また、旧字体なら、こんな「なぞなぞ」も出来た。
「戀には、心も言 もなし」。さて、何という字になりました? 「戀」から下の「心」と「言 」をとってしまうと、「絲」が残る。答えは「糸」です。古くは「絲」と書きました。
日本人は、なぞなぞが昔から好きで、室町時代の人々の作った「なぞなぞ」も残っています。書名は『後奈良院御撰何曽』。では、その中から、今でも同じ字を書くなぞを出しますから、あててみて下さい。
第一問。「嵐は山を去て、軒のへんにあり」。さて、何という言葉が出来上りました? 答えは、「風車 」。「嵐」という字から「山」をとると「風」という字になります。「軒」という字の偏だけをとると「車」ですから。
第二問。「上を見れば下にあり、下を見れば上にあり、母のはらをとりて、子のかたにあり」。さて、答えは? 「一」です。「一」は、「上」の字では下にありますし、「下」の字では上にあります。「母」という字では、真ん中、つまり腹にある。「子」という字では、真ん中より少し上の肩の部分にあるからです。答えを聞くと、なあんだと思う気持が何とも言えないですね。
じゃあ、よく似た問題で、こういうのはいかが。「かみはかみにあり、しもはしもにあり」。何という字でしょうか? 答えは、「卜」です。「うらなう」とか「うらない」と読む字ですね。「上」「下」の字をよく見れば、「卜」の字が含まれてました。
では、こんななぞは? 「山を飛ぶ嵐に、虫は果て、鳥来る」。どんな字になりました?
まず、「嵐」から、「山」の部分を飛ばして下さい。「風」が残ります。「風」の字から、「虫」の部分を取り去って、代わりに「鳥」の字を入れて下さい。「鳳」という字ができますね。「鳳」が答えです。
「紅の糸、くさりて虫となる」。なんぞ?
そう、「虹」です。「廿人木にのぼる」。はて、何という字に?「茶」です。「廿人木」を合わせて一字にして下さい。では、最後に「梅の木をみづにたてかへよ」。なんぞ? 「海」。これは簡単でしたね。いつまでも続けていたい「なんぞ(なぞ)遊び」です。
(以上は、山口仲美『言葉の探検』小学館より。) |
|
|
|
 |
 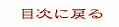 |
 |
|