 |
|
 |
|
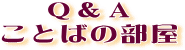
| Q. |
「とつぐ」って「お嫁に行く」の意味だと思っていたのですが、平安時代の作品を読んでいたら奇妙な用例に出くわしました。昔の意味を教えてください。(12/9更新) |
| A. |
つい最近、授業で学生たちと『今昔物語集』巻四の第六話を読んでいたときのことです。その話は、修行を積んだ僧であったはずなのに、外出先で川に溺れかかっている女を助け、ついつい女の魅力に負けて、男の欲望を達せんとしてしまう話です。。
女の人を抱きかかえ、行為に及ぼうとした瞬間、女の人は、師である老僧の姿に変わってしまいました。弟子の僧の悟りの度合いを試そうとして、女の姿を借りていたに過ぎなかったのですね。僧はまんまとひっかかった。まだまだ修行が足りなかったのです。老僧はこの時とばかりに、弟子の僧を責め立てました。欲望を遂げようとした瞬間の姿勢を変えさせずに、老僧はこう言い放ちました。
「汝ヂ 愛欲ヲオコシテ 此クノゴトク為り、速ニ 我レヲ 娶(とつぐ)ベシ。」
私は、この箇所をさらりと読むだけで次の文に移ろうとしたのです。その時、一人の女子学生が怪訝な顔で「『娶(とつ)ぐ』って、なに?」と隣の学生に聞いています。私は困りました。分からない言葉の解説をしつつ、進んできた手前、説明せざるを得ないのです。
「『娶ぐ』というのは、『嫁ぐ』とか『婚ぐ』って書くこともあるけれど、現代語で言えば、エッチすることね。」
辞書に書いてあるような「交接する」とか「交合する」とかと説明しても、よく分からないであろう。学生に分かってもらうように解説するのが一番だと考えてとっさに答えたのでした。ところが、これは分かりすぎたらしい。
授業が終わると、「娶ぐ」の意味を聞いていた女子学生がやってきて、私に念を押しました。
「先生、『とつぐ』って、エッチするの意味なんですか? 『嫁ぎ先』とか『私は嫁いで行きます』の『嫁ぐ』と同じ言葉なんですか?」
「そうね。同一の語と言っていいわね。」
その女子学生はつぶやきました。
「ショックだなぁ。『嫁ぐ』って、古風な感じのする良い言葉だと思っていたのに。そんな意味があるなんて使う気がしなくなっちゃった。」
私は去っていく女子学生の姿を目で追いながら、「とつぐ」が、現在では「嫁に行く」「嫁入りする」の意味でしか用いられていないことを改めて認識させられたのであります。
昔は、もっとそのものずばりの意味で用いられていたんですね。
<「とつぐ」の本格的な意味の考証については、山口仲美「『とつぐ文学』」新編日本古典文学全集35・今昔物語集 月報49号 1999年3月 をご覧下さい。>
|
|
|
|
 |
 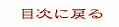 |
 |
|