 |
|
 |
|
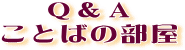
| Q. |
日本の首都「東京」を「とうけい」と言っていた時代があったと聞いて、驚きましたが、それは何時のことですか?(3/21更新) |
| A. |
「日本の首都は?」と聞かれたら、私たち日本人は、「とうきょう」と答えます。それ以外の読み方は、考えられない。「とうけい」なんて読んだら、軽蔑されてしまいます。
でも、「とうけい」と言っても正しかった時期があったんですね。「東京」という地名が出来たのは、明治元年七月十七日の詔書によってです。その詔書には、こうあります。
江戸は東国第一の大鎮、四方輻湊の地、 宜しく親臨以て其政を視るべし。因て自 今江戸を称して東京とせん。
「江戸は、東国で一番の中心地で、四方から人や物が寄り集まってくる所である。天子自らその場所に行き政治をするのがよい。よって今から江戸を東京と呼ぶことにする」というのです。それまで「江戸」とよばれて
いた所を「東京」に改称したのです。その時は、「とうきょう」でも「とうけい」でもよかった。
というのは、それ以前の書物には、地名としての「東京」は無いんですけど、「東の方にある都」の意味で、「東京」という言葉はあった。具体的には、中国の洛陽の地を指したり、日本だったら平安京の左京に当たる東の区域を指したりしたんです。この「東京」は、「とうきょう」「とうけい」の両方の読み方があったからです。
明治元年になって、地名として「東京」が使われるようになった。その時も、「とうけい」「とうきょう」のどちらの読みでもよかった。飛田良文さんは、両方の読み方を丹念に調査していらっしゃるので、それを参考にして例を挙げてみます。まず、「とうけい」の例。
「東ケヰ府貫ゾク小林金ベイ」
明治五年二月二十二日の「東京日々新聞」の例です。東京府管轄の小林金ベイさんが、話題です。「とうけい」です。
「まだ東京を江戸と申しました頃」
明治十七年三遊亭円朝の講じた「怪談牡丹燈篭」の速記記録です。「文三だけは東京に居る叔父の許へ引取られることになり」(二葉亭四迷『浮雲』)などの例もあります。
こんなふうに、「東京」を「とうけい」と読む例は、明治時代の終わり頃まで続いています。
一方、「とうきょう」と読む例は、「大江戸の、都もいつか東京 と」(坪内逍遥『当世書生気質』)などと、明治時代の初めから見られます。つまり、明治時代の終わり頃までは、「東京」は「とうけい」と読んでも「とうきょう」と読んでもよかったんです。
ですが、それまでの都「京都」に対しては「東京 」の読みの方が受け入れやすい。また、国定教科書が「とうきょう」の読みを採用した。こうして、しだいに「とうきょう」の読みに統一され、今日に至ったと言うわけです。 そのうち、飛行場の掲示板で見かける「TOKIO(トキオ)」などと読まれる日がやってくるかもしれませんよ。
(『山口仲美の言葉の探検』小学館 より) |
|
|
|
 |
 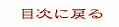 |
 |
|