 |
|
 |
|
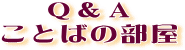
| Q. |
「ホゾをかむ」って、いいますが、「ホゾ」ってなんですか?(12/7更新) |
| A. |
「ホゾをかむ」というのは、すでに及ばないことを悔やむ気持を表わす慣用句ですね。もうこんな言い方を、若者たちは知るまいと寂しい気持を抱きながら、女子大生たちに聞いてみました。
すると、知っていたんです。短文まで作ってくれました。「試験のヤマがはずれて、ホゾをかむ思いだった」「漢文学の単位を落としてホゾをかむ」などと。「『ホゾをかむ』の意味が分からなくて、ホゾをかんだ」というお茶目な短文もありました。このお茶目さんは、余白にこんなことを書いていました。「ところで、ホゾって、何ですか? 体の一部ではないかと思うのですが…」
なあるほど。全体の意味はつかめるのですが、ホゾが何だか分からなくなっているのです。ホゾではなくホホ(頬)だと思い込んでいた人もいます。間違って頬を噛むと悔しいから、悔やむ気持ちを表すと独り合点をしていたそうです。
ホゾは、臍のことですが、学生たちの答えを聞いているうちに気になりはじめたことがあります。なぜ、「ヘソを噛む」とは言わないんでしょうか? ヘソという言葉は、そんなに新しいのでしょうか?
ホゾとヘソの探検に乗り出してみました。
調べてみますと、古くから、「ホゾ」(昔は『ホソ』という発音です)という言葉と、「ヘソ」という言葉は、ともにあるんですね。でも、「ホゾ」の方が、よく用いられる言葉だったようです。平安時代の『宇津保物語』には、「ホゾ」も「ヘソ」も出てきますが、「ホゾ」の方が多く、現在の「へその緒」は、全て「ホゾの緒」と「ホゾ」の語を使って表現しています。
さらに、「ヘソ」の語は、「ホゾ」よりも俗っぽい言い方だった。そのころの辞書には、「ホゾー俗にヘソと云ふ」(『和名類聚抄』)と記されているんです。文章に書いたり、漢文を読み下したりする時には、「ホゾ」を用いています。
「ホゾをかむ」は、中国の『春秋左伝』にある「噬臍(ぜいせい)」という漢語を読み下して出来た慣用句。ですから「ヘソをかむ」とは読み下さずに、「ホゾをかむ」とよみ下したんですね。
「ヘソ」の語が、「ホゾ」よりもよく用いられ出すのは、江戸時代以後のこと。
それにしても、ヘソをかんだりすることが、なぜ、すでに及ばないことを悔やむ気持ちを表すのでしょうか? 自分で自分のヘソをかもうとしても、届かずにどうにもならない。それは、チャンスを失って、後で悔やんでも及ばないのに似ている。そこから、「ホゾをかむ」の意味が出てきたと言われています。 よく似た諺に、「犬の尾を食うて回る」というのがあります。犬が、自分のしっぽをくわえようとしてもくわえられずにぐるぐる回る。苦労が多いわりには報われないことのたとえですね。とすると、人間も犬と同じようなことをしてみようって思ったんでしょうか? なお捜査を続行してみます。
(以上は、私の著書『言葉の探検』小学館の一章からです。) |
|
|
|
 |
 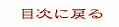 |
 |
|