 |
|
 |
|
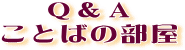
| Q. |
鶯の「ホーホケキョー」の声は「法法華経」の意味に掛けてあるのだと耳にした事があるのですが、本当ですか?(4/29更新) |
| A. |
私たちは、鶯の声をずっと昔から、「ホーホケキョー」と聞いてきたと思っています。けれども、「ホーホケキョー」と聞くのは、わずか江戸時代から。
それ以前は、時代によって実にさまざまな聞き方をしています。それらについては、拙著『ちんちん千鳥の鳴く声は─日本人の聴いた鳥の声─』(大修館書店)を参照してください。 ここでは、鶯の声を「ホーホケキョー」と聞き始めた江戸時代以降のことに焦点を絞って述べておくことにします。
江戸時代は、言うまでもなく仏教が盛ん。そんな状況のなかで鶯の澄んだ美声を聞いていると、穢れた身も心も洗われるようなすがすがしさを覚えますね。そうした気持が仏道にちなむ「法華経」の聞き方を生み出したと察せられます。
鶯も 声はるの日の ながじゅず長数珠に ほう法華経を 繰り返し鳴く (『万載 狂歌集』)
鶯の声が「法華経」の意味で聞かれていたことは確かです。それまでも鶯の声は、「ホーホキ」「ヒートク」「ツーキヒホシ」などと、ハ行音とカ行音を中心にその声が写されて来ているので、「ホーホケキョー」の声の生まれる下地は既に整えられていたのです。
「法華経」の意味を聞き取った江戸時代の人々は、鶯の声を、どんな鳥の声よりも珍重しました。こんな狂歌があります。
慈悲心も 仏法僧も 一声の ほう法華経に しくものぞなき (『蜀山百首』)
慈悲心も仏法僧も鳥の名前。それぞれ、鳴き声がそう聞えることから名づけられたもの。「鶯の『ほう法華経』の一声は、同じく美声で仏道にちなむ鳴き声を持つ慈悲心鳥や仏法僧にも勝っている」という意味の歌。江戸時代では、概して鳥の声を宗教的な聞き取り方をしていたのです。
慈悲心鳥は、現在のジュウイチ。鳴き声を現在では「ジュウイチー」と聞くところから。仏法僧は、現在のコノハズク。
現代は、江戸時代ほど仏教の影響が強くない時代。そのため、私たちは、鶯の声に「法華経」の意味があったことをすっかり忘れてしまい、「ホーホケキョー」は、鶯の声を写すだけの擬音語だと思っています。だから、「鶯が可愛い声でホウホケキョウ」(文部省唱歌「梅に鶯」)と、「可愛い声」にも思うのです。
(上記は、『日本語学』21巻11号臨時増刊号、平成14年11月に掲載したもの)
|
|
|
|
 |
 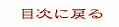 |
 |
|