 |
|
 |
|
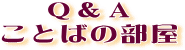
| Q. |
天狗はどんな声で鳴くんですか?(12/14更新) |
| A. |
子供の頃、よく遊びに行った家の鴨居に天狗の面が掛けてありました。真っ赤な顔に高く突き出た鼻を持った妖怪(ようかい)がひたすら恐かったのを記憶しています。。大人になって、室町時代の狂言台本にも目を通すようになった時、思わず目を見張るようなことに出くわしました。天狗が鳴いていたのです!
犬の鳴き声を江戸時代までの日本人が「びよ」と聞いて来たことを知った時の驚きを、小著『犬は「びよ」と鳴いていた』(光文社)に記しましたが、それと同じくらい意表を突かれたんです。
狂言台本「天狗(てんぐ)の嫁取り」は、天狗同士の結婚披露のめでたい様子を描いた狂言。宴を仕切るのは、長老格の大天狗。セリフの後に、大天狗は「ひいよろよろ」と鳴き声をあげていたのです。家来たちは、「ひょうよろよろ」「ひいひいひ」。
また、「婿入り天狗」という狂言台本でも、天狗が鳴いていました。舅(しゅうと)、婿、花嫁、家来、すべての天狗たちがセリフの後に、あるいはセリフ代わりに「ひいひい」の声をあげていました。妖怪の天狗が、鳥のようにおどけた鳴き声をあげていたのです。
一体これらの鳴き声は、何なのでしょうか? 「天狗の嫁取り」の台本をよく見ると、「ひいよろよろ」の声の下に小書きで「鳶(とび)の鳴き声のまねなり」と書いてあります。鳶の鳴き声と同じなのです。
「柿山伏」という狂言には、鳶が登場します。その鳴き声は、天狗と同じく「ひいよろよろ」「ひいひい」。現代では、鳶の声を「ぴーひょろ」とパ行音で聞きますが、昔は「ひいよろ」とハ行音で聞いていました。でも、なぜ天狗は鳶の鳴き声をあげるのでしょうか? 天狗は妖怪なのですから、どんな鳴き声をあげてもよさそうなものです。よりによって、なぜ鳶の声なのでしょうか?
調べてみると、天狗と鳶との深い関係が浮かび上がってきました。平安末期の説話集に「今昔物語集」があります。そこでは、年功を積んだ鳶は天狗になり、逆に天狗の妖術が敗れると、羽根の折れた鳶になって死んでいます。鳶と天狗は、変化自在の関係にあると信じられていたのです。だから、天狗の鳴き声は、鳶の鳴き声なのです。
そういえば、江戸時代には『天狗そろへ』という絵本が出ています。まあ、言ってみれば子供の楽しむ天狗図鑑。山伏姿の天狗もいれば、僧侶姿の天狗もいます。天狗ごとに違ったいでたちをしているのですが、不思議なことに多くの天狗の背中には大きな翼が付いているのです。その翼は、うろこ状の模様をもち、翼の先端が割れており、鳶の羽根を思わせます。天狗が鳶の化身である証拠。また、鼻は、人間の鼻をぐっと高くしただけに見える天狗もいますが、多くは、鼻先が鋭く尖って鉤状になっています。天狗の鼻は、なぜ高い? 実は、天狗の鼻は、もともとは猛禽類の鳶の鉤状のくちばしをかたどったものだからではあるまいか。これは、私の推測です。鳶と天狗の深い関係を知ると、天狗が身近な鳥の面影を帯び、親近感が湧いてきますね。
(共同通信社 山口仲美『二月の随想―天狗が鳴いた―』2003年2月の配信原稿を手直しして掲載しました。いろいろな地方新聞に掲載されています。)
|
|
|
|
 |
 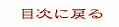 |
 |
|