 |
<学術論文> |
 |
|
(1) |
昭和42年 7月 |
単著 |
『国文(お茶の水女子大)』 27号 |
|
|
「説話文学の文体研究(一)―説話集における和漢混淆の度合―」 |
|
|
(2) |
昭和43年 7月 |
単著 |
『国文(お茶の水女子大)』 29号 |
|
|
「説話文学の文体研究(二)―戦記文学と比較して―」 |
|
|
(3) |
昭和44年 8月 |
単著 |
『国文学(学燈社)』14巻11号 |
|
|
「比喩の表現論的性格と文体論への応用(1)」 |
|
|
(4) |
昭和44年 9月 |
単著 |
『国文学(学燈社)』14巻12号 |
|
|
「比喩の表現論的性格と文体論への応用(2)」 |
|
|
(5) |
昭和44年12月 |
単著 |
『国語学』79集 |
|
|
「今昔物語集の文体に関する一考察―『事無限シ』をめぐって―」 |
|
|
(6) |
昭和45年11月 |
単著 |
『国語と国文学』47巻11号 |
|
|
「今昔物語集の文体について(1)―直喩表現の分析から―」 |
|
|
(7) |
昭和45年12月 |
単著 |
『国語と国文学』47巻12号 |
|
|
「今昔物語集の文体について(2)―直喩表現の分析から―」 |
|
|
(8) |
昭和46年 1月 |
単著 |
『共立女子短期大学部紀要』14号 |
|
|
「平安時代の象徴詞―性格とその変遷過程―」 |
|
|
(9) |
昭和47年 3月 |
単著 |
『説話文学研究』6号 |
|
|
「かきけつやうにうせぬ」 |
|
|
(10) |
昭和47年 5月 |
単著 |
『王朝』(中央図書出版社) 5冊 |
|
|
「今昔物語集の象徴詞―表現論的性格―」 |
|
|
(11) |
昭和48年 1月 |
単著 |
『共立女子短期大学部紀要』16号 |
|
|
「続中古象徴詞の語音構造―撥音・長音・促音に関する問題を含む語例を中心に―」 |
|
|
(12) |
昭和48年 6月 |
単著 |
『国語学』93集 |
|
|
「中古象徴詞の語音構造―清濁に問題のある語例を中心に―」 |
|
|
(13) |
昭和49年 9月 |
単著 |
『国語学』98集 |
|
|
「平安朝文章史研究の一視点―文連接法を中心に―」 |
|
|
(14) |
昭和49年11月 |
単著 |
『日本の説話・七巻』(東京美術) |
|
|
「説話文学の表現」 |
|
|
(15) |
昭和50年 9月 |
単著 |
『寝覚物語対校・平安文学論集』
(風間書房) |
|
|
「平中物語の文体」 |
|
|
(16) |
昭和51年 5月 |
単著 |
『表現学論考』
(今井文男教授還暦記念論集刊行委員会) |
|
|
「歌物語における歴史的現在法」 |
|
|
(17) |
昭和51年11月 |
単著 |
『国語国文』45巻11号 |
|
|
「源氏物語の比喩表現と作者(上)」 |
|
|
(18) |
昭和51年12月 |
単著 |
『国語国文』45巻12号 |
|
|
「源氏物語の比喩表現と作者(下)」 |
|
|
(19) |
昭和52年 9月 |
単著 |
『日本古典文学会会報』54号 |
|
|
「平安時代の動物の鳴き声」 |
|
|
(20) |
昭和52年 9月 |
単著 |
『表現研究』26号 |
|
|
「歴史的現在法の文体論的意味―平安日記文学を中心として―」 |
|
|
(21) |
昭和52年11月 |
単著 |
『松村明教授還暦記念・国語学と国語史』
(明治書院) |
|
|
「浜松中納言物語と夜の寝覚の作者―比喩表現をてがかりとして―」 |
|
|
(22) |
昭和52年12月 |
単著 |
『日本文学』294号 |
|
|
「比喩表現に見る時代性」 |
|
|
(23) |
昭和53年 3月 |
単著 |
『国語学』112集 |
|
|
「平安仮名文における朧化性の問題―源氏物語を中心にして―」 |
|
|
(24) |
昭和54年 2月 |
単著 |
『共立女子短期大学文科紀要』22号 |
|
|
「竹取物語の文体と成立過程」 |
|
|
(25) |
昭和55年 5月 |
単著 |
『国語語彙史の研究・一』(和泉書院) |
|
|
「平安仮名文における形容詞・形容動詞」 |
|
|
(26) |
昭和56年 1月 |
単著 |
『国文学(学燈社)』26巻1号 |
|
|
「蜻蛉日記―こころのことば―」 |
|
|
(27) |
昭和56年 4月 |
単著 |
『一冊の講座・蜻蛉日記』(有精堂) |
|
|
「蜻蛉日記の語法」 |
|
|
(28) |
昭和56年 5月 |
単著 |
『解釈と鑑賞』46巻5号 |
|
|
「文体論の新しい課題」 |
|
|
(29) |
昭和57年 1月 |
単著 |
『講座日本語学・四巻』(明治書院) |
|
|
「感覚・感情語彙の歴史」 |
|
|
(30) |
昭和57年 2月 |
単著 |
『日本古典文学会会報』90号 |
|
|
「王朝文学における『つと』の意味」 |
|
|
(31) |
昭和57年 5月 |
単著 |
『古代の語彙・講座日本語の語彙』 三巻
(明治書院) |
|
|
「源氏物語の語彙ー象徴詞を中心にー」 |
|
|
(32) |
昭和57年 8月 |
単著 |
『源氏物語の探求』七輯 (風間書房) |
|
|
「源氏物語の表現―並列形容語の分析から―」 |
|
|
(33) |
昭和58年 7月 |
単著 |
『研究資料日本古典文学』十二巻
(明治書院) |
|
|
「副詞・接続詞」 |
|
|
(34) |
昭和58年 8月 |
単著 |
『日本文学』32巻8号 |
|
|
「『つぶつぶと』肥えたまへる人」 |
|
|
(35) |
昭和58年10月 |
単著 |
『国語と国文学』60巻10号 |
|
|
「源氏物語の象徴詞―その独自の用法―」 |
|
|
(36) |
昭和59年 6月 |
単著 |
『研究資料日本文法・構文編』八巻
(明治書院) |
|
|
「文章の展開」 |
|
|
(37) |
昭和60年 2月 |
単著 |
『共立女子短期大学文科紀要』28号 |
|
|
「名づけの志向―売薬名―」 |
|
|
(38) |
昭和60年 3月 |
単著 |
『日本の美学』4号 |
|
|
「鳥声の系譜」 |
|
|
(39) |
昭和60年 3月 |
単著 |
『日本語学』4巻3号 |
|
|
「音とことば―哀切な鳥声(1)―」 |
|
|
(40) |
昭和60年 4月 |
単著 |
『日本語学』4巻4号 |
|
|
「音とことば―哀切な鳥声(2)―」 |
|
|
(41) |
昭和60年 5月 |
単著 |
『日本語学』4巻5号 |
|
|
「音とことば―怪鳥ヌエの声―」 |
|
|
(42) |
昭和60年 6月 |
単著 |
『日本語学』4巻6号 |
|
|
「音とことば―ちんちん千鳥のなく声は―」 |
|
|
(43) |
昭和60年 8月 |
単著 |
『日本語学』4巻8号 |
|
|
「音とことば―ちいちいぱっぱ考―」 |
|
|
(44) |
昭和60年 9月 |
単著 |
『日本語学』4巻9号 |
|
|
「音とことば―ふくろうの声―」 |
|
|
(45) |
昭和60年10月 |
単著 |
『日本語学』4巻10号 |
|
|
「音とことば―狂言の鳥声(1)ニワトリ―」 |
|
|
(46) |
昭和60年11月 |
単著 |
『日本語学』4巻11号 |
|
|
「音とことば―狂言の鳥声(2)―『ほおん』は梟声か―」 |
|
|
(47) |
昭和60年12月 |
単著 |
『日本語学』4巻12号 |
|
|
「音とことば―鳴け鳴けトンビ―」 |
|
|
(48) |
昭和60年12月 |
単著 |
『NOMAプレスサービス』 |
|
|
「知っておきたいネーミングの秘密」 |
|
|
(49) |
昭和61年 3月 |
単著 |
『築島裕博士還暦記念国語学論集』
(明治書院) |
|
|
「狂言の擬声語」 |
|
|
(50) |
昭和61年 7月 |
単著 |
『日本語学』5巻7号 |
|
|
「古典の擬音語・擬態語ー掛詞式の用法を中心にー」 |
|
|
(51) |
昭和61年10月 |
単著 |
『松村明教授古稀記念国語研究論集』
(明治書院) |
|
|
「写声語の一性格」 |
|
|
(52) |
昭和61年11月 |
単著 |
『国文学(学燈社)』31巻14号 |
|
|
「題をつける際の発想」 |
|
|
(53) |
昭和61年12月 |
単著 |
『国語語彙史の研究・七』(和泉書院) |
|
|
「音象徴語研究の一視点」 |
|
|
(54) |
昭和62年 3月 |
単著 |
『国文法講座』四巻(明治書院) |
|
|
「伊勢物語の文法」 |
|
|
(55) |
昭和62年12月 |
単著 |
『私学研修』107・108合併号 |
|
|
「中古象徴詞の研究―『今昔物語集』を中心に―」 |
|
|
(56) |
昭和63年 1月 |
単著 |
『日本の文学』2巻(有精堂) |
|
|
「和泉式部日記の文体」 |
|
|
(57) |
昭和63年 5月 |
単著 |
『別冊国文学(学燈社)』34号 |
|
|
「竹取物語・伊勢物語のことば」 |
|
|
(58) |
昭和63年 6月 |
単著 |
『月刊 日本語』6号 |
|
|
「Gパン姿の名文」 |
|
|
(59) |
昭和63年 7月 |
単著 |
『むらさき』25輯 |
|
|
「源氏物語の擬人法」 |
|
|
(60) |
昭和63年 7月 |
単著 |
『ことば(NHK学園)』26号 |
|
|
「ツルの一声」 |
|
|
(61) |
昭和63年 7月 |
単著 |
『ぶっくれっと』(三省堂)75号 |
|
|
「『ぼろおん』はホラ貝の音? (1)」 |
|
|
(62) |
昭和63年 9月 |
単著 |
『ぶっくれっと』(三省堂)76号 |
|
|
「『ぼろおん』はホラ貝の音? (2)」 |
|
|
(63) |
昭和63年11月 |
単著 |
『ぶっくれっと』(三省堂)77号 |
|
|
「『ぼろおん』はホラ貝の音? (3)」 |
|
|
(64) |
平成 1年 4月 |
単著 |
『古典への招待』(日本放送出版協会) |
|
|
「日本の説話」 |
|
|
(65) |
平成 1年 5月 |
単著 |
『新日本古典文学大系月報』5号 |
|
|
「北の方の実在感」 |
|
|
(66) |
平成 1年 6月 |
単著 |
『月刊 言語』18巻6号 |
|
|
「ウズラの鳴き声」 |
|
|
(67) |
平成 1年 7月 |
単著 |
『日本語音声』NO・2 |
|
|
「ハトの鳴き声」 |
|
|
(68) |
平成 1年11月 |
単著 |
『国語教室』38号 |
|
|
「ヒバリは何とさえずるか」 |
|
|
(69) |
平成 2年 1月 |
単著 |
『国文(お茶の水女子大)』72号 |
|
|
「落窪物語の会話文―人物造型の方法―」 |
|
|
(70) |
平成 2年11月 |
単著 |
『月刊 日本語』3巻11号 |
|
|
「男と女の会話学―『源氏物語』をテキストとして―」 |
|
|
(71) |
平成 2年12月 |
単著 |
『月刊 日本語』3巻12号 |
|
|
「はかなき恋―光源氏と夕顔―」 |
|
|
(72) |
平成 3年 1月 |
単著 |
『月刊 日本語』4巻1号 |
|
|
「秘められたる恋―光源氏と藤壷―」 |
|
|
(73) |
平成 3年 2月 |
単著 |
『月刊 日本語』4巻2号 |
|
|
「誇り高き女性たち―妻と愛人―」 |
|
|
(74) |
平成 3年 7月 |
単著 |
『講座日本語と日本語教育』十巻
(明治書院) |
|
|
「和文体の歴史」 |
|
|
(75) |
平成 4年 1月 |
単著 |
『月刊 言語』21巻1号 |
|
|
「動物たちの声を聞く(1)―昔の犬は何と鳴く―」 |
|
|
(76) |
平成 4年 2月 |
単著 |
『月刊 言語』21巻2号 |
|
|
「動物たちの声を聞く(2)―ニャンとせう―」 |
|
|
(77) |
平成 4年 3月 |
単著 |
『月刊 言語』21巻3号 |
|
|
「動物たちの声を聞く(3)―チウき殺してやらふ―」 |
|
|
(78) |
平成 4年 4月 |
単著 |
『月刊 言語』21巻4号 |
|
|
「動物たちの声を聞く(4)―モウモウぎうの音も出ませぬ―」 |
|
|
(79) |
平成 4年 5月 |
単著 |
『月刊 言語』21巻5号 |
|
|
「動物たちの声を聞く(5)―イヒヒンヒンと笑ふて別れぬ―」 |
|
|
(80) |
平成 4年 6月 |
単著 |
『月刊 言語』21巻6号 |
|
|
「動物たちの声を聞く(6)―われは狐ぢゃこんこんくゎいくゎい―」 |
|
|
(81) |
平成 4年 8月 |
単著 |
『源氏物語講座』六巻 (勉誠社) |
|
|
「源氏物語の恋愛情緒表現」 |
|
|
(82) |
平成 6年 2月 |
単著 |
『月刊 言語』23巻2号 |
|
|
「平安の文体・平成の文体」 |
|
|
(83) |
平成 6年 9月 |
単著 |
『表現研究』60号 |
|
|
「谷崎潤一郎『細雪』の表現―『源氏物語』の影響―」 |
|
|
(84) |
平成 6年 9月 |
単著 |
『国文学』学燈社 39巻10号 |
|
|
「敬語の運用に注目して古典を解釈する―今昔物語集―」 |
|
|
(85) |
平成 7年 1月 |
単著 |
『時代別 文学史事典』有精堂 |
|
|
「仮名の成立と平安朝文学」 |
|
|
(86) |
平成 7年10月 |
単著 |
『王朝日記の新研究』笠間書院 |
|
|
「『和泉式部日記』作者の意図―物語をめざして―」 |
|
|
(87) |
平成 7年10月 |
単著 |
『論集平安文学』3号 |
|
|
「中年の恋―光源氏と玉鬘―」 |
|
|
(88) |
平成 7年12月 |
単著 |
『国文学』学燈社 40巻14号 |
|
|
「尊敬表現の現在―衰退の流れのなかで―」 |
|
|
(89) |
平成 8年 6月 |
単著 |
『山口明穂教授還暦記念 国語学論集』
(明治書院) |
|
|
「モモンガの声―擬声語に関する一考察―」 |
|
|
(90) |
平成 8年10月 |
単著 |
『国語語彙史の研究・十六』(和泉書院) |
|
|
「ツクツクボウシの鳴く声は―擬声語の史的推移―」 |
|
|
(91) |
平成10年11月 |
単著 |
『源氏物語研究集成―源氏物語の表現と文体上』
(風間書房) |
|
|
「源氏物語の『男の表現』・『女の表現』」 |
|
|
(92) |
平成11年 3月 |
単著 |
『新編日本古典文学全集35・今昔物語集一』
月報49 |
|
|
「『とつぐ』文学」 |
|
|
(93) |
平成12年 3月 |
単著 |
『埼玉大学紀要・教養学部』35巻2号 |
|
|
「北京における日本語教育に関する現状報告と提言」 |
|
|
(94) |
平成12年 3月 |
単著 |
『ぶっくれっと』141号 |
|
|
「日本語が外に出るとき(上)・日本語草子1」 |
|
|
(95) |
平成12年 5月 |
単著 |
『ぶっくれっと』142号 |
|
|
「日本語が外に出るとき(下)・日本語草子2」 |
|
|
(96) |
平成12年 6月 |
単著 |
『日本語学』19巻6号 |
|
|
「味と味覚を表す語彙と表現」 |
|
|
(97) |
平成12年 7月 |
単著 |
『ぶっくれっと』143号 |
|
|
「敬語をこう考える(上)・日本語草子3」 |
|
|
(98) |
平成12年 9月 |
単著 |
『ぶっくれっと』144号 |
|
|
「敬語をこう考える(下)・日本語草子4」 |
|
|
(99) |
平成12年11月 |
単著 |
『ぶっくれっと』145号 |
|
|
「大型国語辞典が求められるもの(上)・日本語草子5」 |
|
|
(100) |
平成12年12月 |
単著 |
『国文学解釈と鑑賞』65巻12号 |
|
|
「源氏物語の言葉と文体」 |
|
|
(101) |
平成13年 1月 |
単著 |
『ぶっくれっと』146号 |
|
|
「大型国語辞典に求められるもの(中)・日本語草子6」 |
|
|
(102) |
平成13年 2月 |
単著 |
『日本語学』20巻2号 |
|
|
「広告表現の変遷」 |
|
|
(103) |
平成13年 3月 |
単著 |
『ぶっくれっと』147号 |
|
|
「大型国語辞典に求められるもの(下)・日本語草子7」 |
|
|
(104) |
平成13年 5月 |
単著 |
『ぶっくれっと』148号 |
|
|
「本の広告表現について(上)・日本語草子8」 |
|
|
(105) |
平成13年 6月 |
単著 |
『SCIENCE OF HUMANITY 』33号 |
|
|
「中国の日本語教育」 |
|
|
(106) |
平成13年 7月 |
単著 |
『ぶっくれっと』149号 |
|
|
「本の広告表現について(下)・日本語草子9」 |
|
|
(107) |
平成13年10年 |
単著 |
『日本語史研究の課題』武蔵野書院 |
|
|
「擬音語・擬態語の変化」 |
|
|
(108) |
平成13年11月 |
単著 |
『ぶっくれっと』151号 |
|
|
「擬音語・擬態語に魅せられる」 |
|
|
(109) |
平成14年 1月 |
単著 |
『ぶっくれっと』152号 |
|
|
「源氏物語味読法」 |
|
|
(110) |
平成14年 3月 |
単著 |
『ぶっくれっと』153号 |
|
|
「『源氏物語』男と女のコミュニケーション |
|
|
(111) |
平成14年11月 |
単著 |
『日本語学』21巻14号 |
|
|
「鶯の『ホーホケキョー』の声は『法法華経』の意味ってほんと?」 |
|
|
(112) |
平成15年10月 |
単著 |
『文学・語学』177号 |
|
|
「歌ことばの展開」 |
|
|
(113) |
平成16年 3月 |
単著 |
『日本アジア研究』創刊号
(埼玉大学大学院文化科学研究科博士後期課程紀要) |
|
|
「内から見た日本語」 |
|
|
(114) |
平成17年 3月 |
単著 |
中村明・野村雅昭・佐久間まゆみ・小宮千鶴子編『表現と文体』明治書院 |
|
|
「オノマトペと文学」 |
|
|
(115) |
平成17年 9月 |
単著 |
『埼玉大学紀要』第41巻第1号 |
|
|
「国語審議会の終焉―国語施策百年史の一コマとして―」 |
|
|
(116) |
平成17年10月 |
単著 |
『築島裕博士傘寿記念 国語学論集』汲古書院 |
|
|
「コミック世界の擬音語・擬態語」 |
|
|
(117) |
平成19年11月 |
単著 |
『みやびブックレット』18号、みやび出版 |
|
|
「清少納言の言語感覚」 |
|
|
(118) |
平成24年3月 |
単著 |
『明治大学 国際日本学研究』第4巻第1号 |
|
|
「奈良時代の擬音語・擬態語」 |
|
|
(119) |
平成25年3月 |
単著 |
『明治大学 国際日本学研究』第5巻第1号 |
|
|
「オノマトペの文法的機能の変遷」 |
|
|
(120) |
平成26年8月 |
単著 |
『清流』21巻8号 |
|
|
「ちょっと意外な言葉の話―ざっくばらん―」 |
|
|
(121) |
平成26年9月 |
単著 |
『清流』21巻9号 |
|
|
「ちょっと意外な言葉の話―おべんちゃら―」 |
|
|
(122) |
平成26年10月 |
単著 |
『清流』21巻10号 |
|
|
「ちょっと意外な言葉の話―総すかん―」 |
|
|
(123) |
平成26年11月 |
単著 |
『清流』21巻11号 |
|
|
「ちょっと意外な言葉の話―じゃじゃ馬―」 |
|
|
(124) |
平成26年12月 |
単著 |
『清流』21巻12号 |
|
|
「ちょっと意外な言葉の話―てんてこ舞い―」 |
|
|
(125) |
平成26年12月 |
単著 |
『清流』22巻1号 |
|
|
「ちょっと意外な言葉の話―とんとん拍子―」 |
|
|
(126) |
平成27年1月 |
単著 |
『清流』22巻2号 |
|
|
「ちょっと意外な言葉の話―ぐる―」 |
|
|
(127) |
平成27年2月 |
単著 |
『清流』22巻3号 |
|
|
「ちょっと意外な言葉の話―とことん―」 |
|
|
(128) |
平成27年3月 |
単著 |
『清流』22巻4号 |
|
|
「ちょっと意外な言葉の話―いちゃもん―」 |
|
|
(129) |
平成27年4月 |
単著 |
『清流』22巻5号 |
|
|
「ちょっと意外な言葉の話―へなちょこ―」 |
|
|
(130) |
平成27年5月 |
単著 |
『清流』22巻6号 |
|
|
「ちょっと意外な言葉の話―たんぽぽ―」 |
|
|
(131) |
平成27年6月 |
単著 |
『清流』22巻7号 |
|
|
「ちょっと意外な言葉の話―ぺんぺん草―」 |
|
|
(132) |
2015年7月 |
単著 |
『清流』22巻8号 |
|
|
「ちょっと意外な言葉の話―パチンコ―」 |
|
|
(133) |
2015年8月 |
単著 |
『清流』22巻9号 |
|
|
「ちょっと意外な言葉の話―ばった屋―」 |
|
|
(134) |
2015年9月 |
単著 |
『清流』22巻10号 |
|
|
「ちょっと意外な言葉の話―ひいらぎ―」 |
|
|
(135) |
2015年9月 |
単著 |
『日本語学』34巻11号 |
|
|
「オノマトペ研究の私的回顧」 |
|
|
(136) |
2015年9月 |
単著 |
NHK出版 |
|
|
「女の才能、花開く」『NHK「100分de名著」ブックス―清少納言 枕草子―』 |
|
|
(137) |
2015年10月 |
単著 |
『清流』22巻11号 |
|
|
「ちょっと意外な言葉の話―はたはた―」 |
|
|
(138) |
2015年11月 |
単著 |
『清流』22巻12号 |
|
|
「ちょっと意外な言葉の話―とろろ汁―」 |
|
 |
 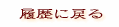 |
 |